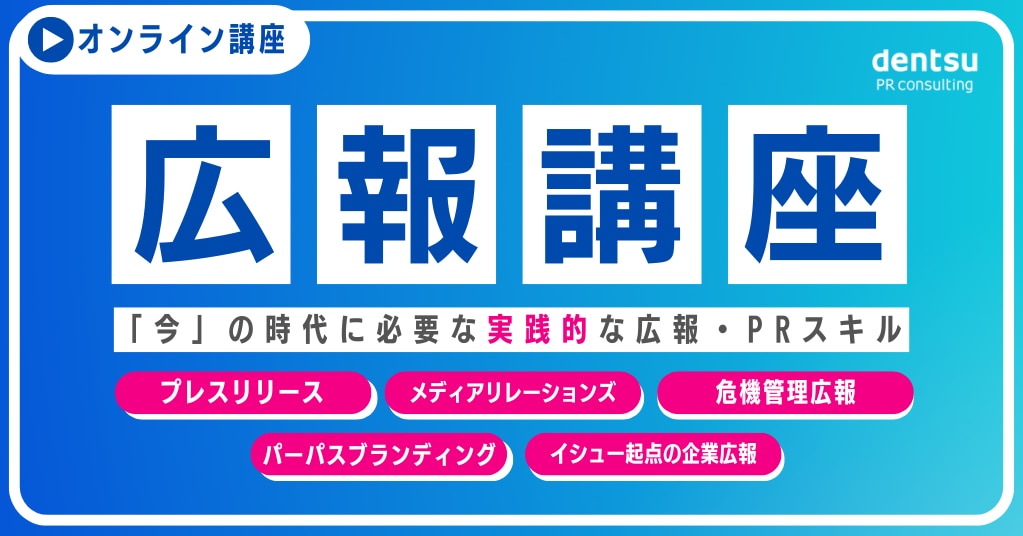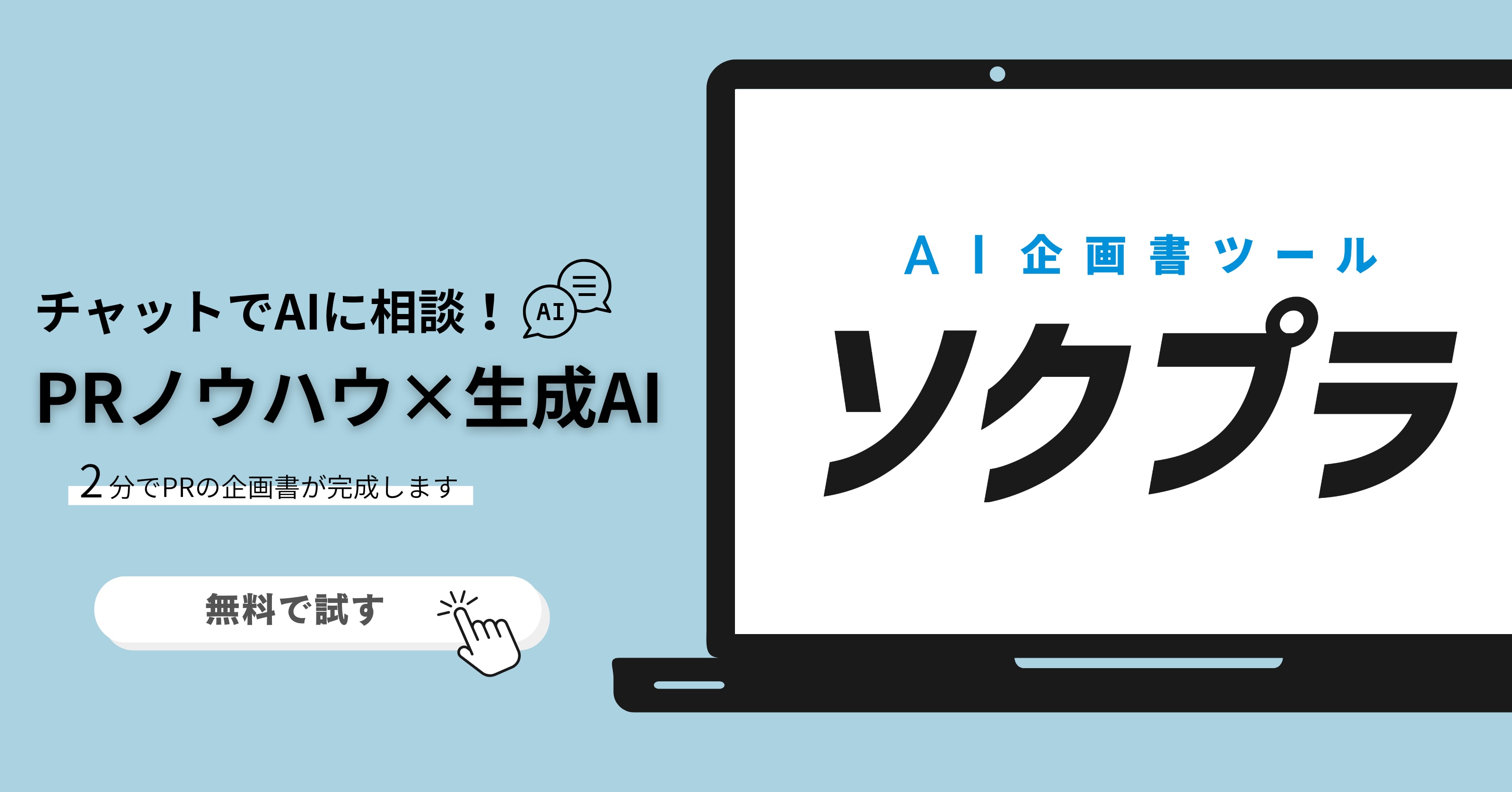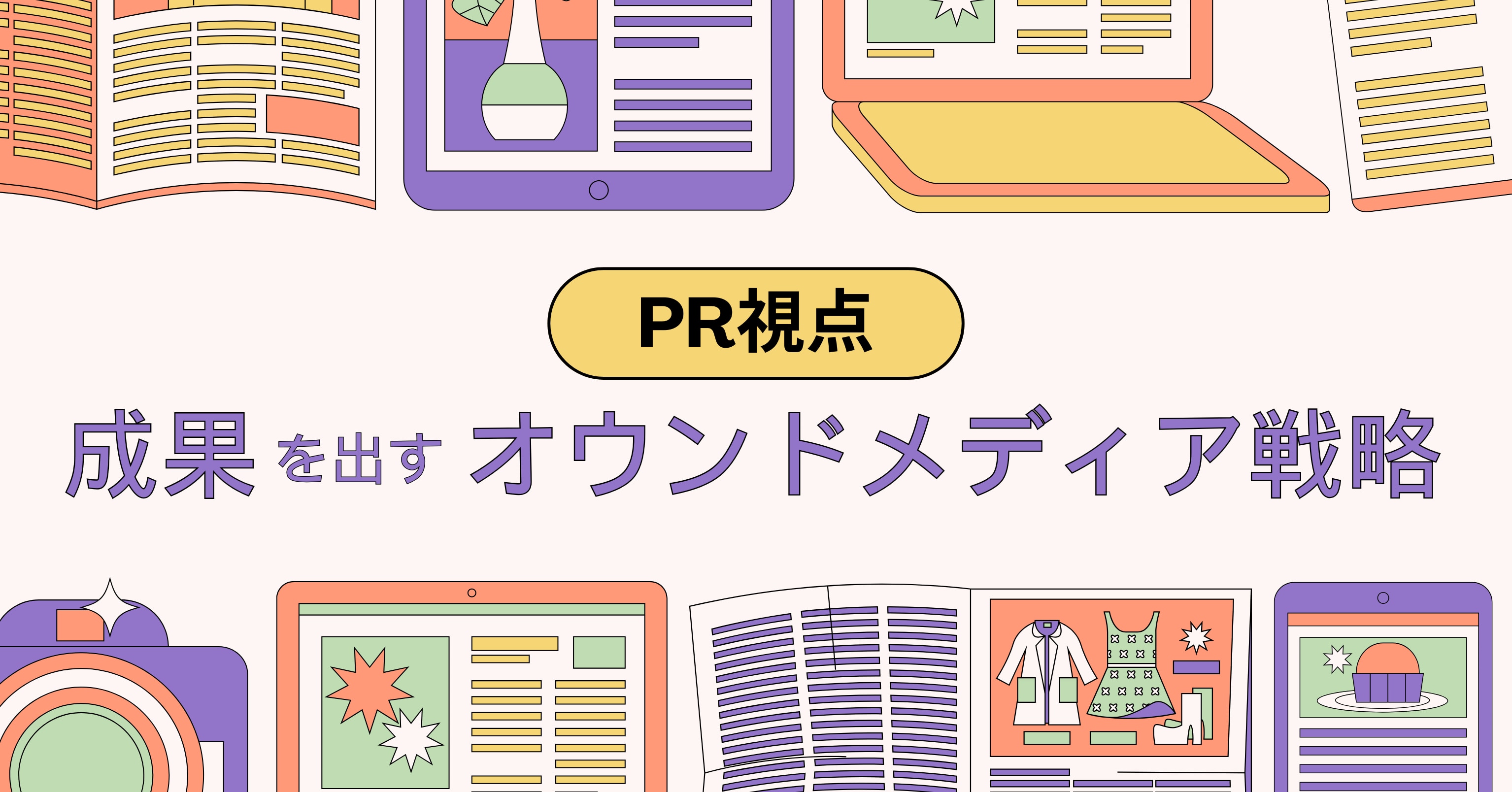
「オウンドメディアとは」から考える、PR視点で成果を出すオウンドメディア戦略
オウンドメディアは、「企業が自由に情報を発信できる場」と捉えられがちです。しかし、その全てが受け入れられるわけではなく、実際には「受け入れられている部分」と「受け取ってもらえない部分」があり、データで可視化されます。つまり、世の中の反応を見ながら、改善できるメディアです。
PR思考とは、企業が伝えたいことと社会が知りたいことの接点を見つけ、コンテンツ設計に活かす発想です。
本記事では、PRのデジタル活用やオウンドメディア戦略の構築などをサポートしている知見をもとに、PR思考によるオウンドメディアについて解説します。
▶電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
▶伝えたい情報を的確に発信するための「PR思考のウェブサイト診断」メニュー資料をダウンロード
目次[非表示]
ウェブサイト構築段階から「PR思考」を
企業のウェブサイトの運営に関して、担当者からは下記のような悩みがよく聞かれます。
・報告された数値レポートは見ているが、効果が実感できない
・改善しようにも、何をどうしたら良いのか分からない
・運営の手応えがなく、使いにくいウェブサイトのように思えてしまう
こういった悩みを解決するためには、問題を一つずつ解決するよりも、根本的な見直しが効果的な場合もあります。
「認知から購買まで一貫して成果を出したい!」
「オシャレで話題になるような、ウェブサイトを作りたい!」
「PV数を高めるために、コンテンツをたくさん制作しなくては...」
「なんか古いから、今っぽくリニューアルを!」など、ウェブサイト制作を担当している方なら、目の前の問題一つ一つに追われてしまうこともあるでしょう。
しかし、問題に着手する前にまず整理したい3つのステップがあります。段階を飛ばさず、順を追って取り組むという点も、実は大きなポイントです。
オウンドメディア戦略における3つのステップ
ステップ❶ 誰にでも見やすい気遣い
「ウェブサイトのルール」ともいえる、基本的な部分です。オウンドメディア、特にウェブサイトの大きな特徴として、誰でもアクセスすることができ、コンテンツを読むことができるという公共性の高さが挙げられます。
ターゲットを意識することは大切ですが、コアとなるターゲット以外のパブリックユーザー(前提知識がない人、視覚障害がある人、多様なデバイスから閲覧する人など)の利用も考慮されていることが、「PR思考」においては重要です。
つまり、誰が、どの環境で見ても、適切な情報にスムーズにアクセスできる設計になっているか、特定のターゲットへ向けたユーザビリティ以上に、全パブリックユーザーに向けたアクセシビリティ設計が不可欠となります。
また、検索して流入してくるパブリックユーザーのための情報の受け皿としての役割と、パブリック全体への情報発信という、適切な役割分担を切り分けて持たせることが必要です。
「購買につながる情報を押し出したい」という考えは、ウェブマーケティングの視点では出てきやすいですが、ウェブサイトの役割はそれだけではありません。まず大前提として「公共性(パブリックネス)」を大切に、誰もがアクセスできる環境を整えましょう。

ステップ❷ 事前のリスクチェック
ポジティブな反応の獲得はもちろん大事ですが、「ネガティブな反応」を起こさせないことも「PR思考」において重要です。いかに事前にリスクチェックし、ネガティブな反応を回避できるかが大事です。
例えば、ウェブサイト上にこのようなコンテンツが残り続けていませんか。
つい最近まで大手企業やメディアで使われていた表現が、今や時流に合わない、ということはよくあります。ネガティブな反応につながるコンテンツが残り続けている原因としてよくあるのは、以下のような点が挙げられます。
・ヒューマンリソースが限られている中で、コンテンツが今の時流に沿っているかまで、常にチェックできない
・チーム内など、同じような視点を持った人のチェックだけだと気付きにくい
では、具体的にはどのようにリスクチェックをしていくと良いのでしょうか。対策として以下のパターンが考えられます。
対策A:ウェブサイト制作を外部の制作会社に依頼する前に、考え得るリスクのチェックリストを準備し、それを基にオリエンテーションを行う
↓
納品されたウェブサイトイメージを、チェックシートに照らし合わせて確認する
対策B:複数人のチームで、ウェブサイト制作・チェックを行う
↓
法務担当者・企業のリスク担当者とも連携し、リスクチェックをしておく
出来上がってからチェックするのでは、判断が甘くなってしまったり、進行スケジュールの関係で修正ができない状況になっていたりすることもあります。
例えば「イクメン」という情報は一見ポジティブでも、実際は「なぜ男性だけ特別視されるの?」「母親だって頑張っている!」などといった、ネガティブな反応を引き起こすリスクが考えられます。
「ポジティブ反応の追求」以前に「リスクチェック」をしておく必要があるのは、まさにこうした理由からです。構想の段階で厳しい目でチェックすることが大切です。
ステップ❸ ターゲットに好意的に伝わるコンテンツ作り
さて、ここからようやく、好意的な反応を得るための内容の検討に入っていきます。ターゲットに好意的に伝わるコンテンツ作りのためには、3つのポイントがあります。
好意的に伝わるための3つのポイント
ポイント① 企業戦略と連動した目標設定
企業の経営視点の戦略と、ウェブサイトの目標設定が連携できていないケースが多くあります。流入数などウェブサイト単体の指標のみでKGI/KPIなど目標設定をするのではなく、企業全体として伝えたいメッセージを伝えていくために、ウェブサイトがどんな役割を果たせばいいのかを逆算して、そのための目標設定をすることが望ましいです。
また、「認知・関心・検討・購買を一気通貫で…」と、ウェブサイトに役割を背負わせ過ぎてしまう例も多くあります。広報・宣伝・マーケティングなど、企業全体のコミュニケーションを考えたときの、一つの手法として捉える視点が大事です。
野球で例えると「1番打者が塁に出て、2番がバントで送って、3~5番の誰かがヒットを打って得点につながって…」と、チーム一人一人の役割が想像できると思います。
ウェブサイトもしかりで、企業戦略全体をチームと捉えたとき、コミュニケーションにおけるウェブサイトの役割をどこに据えるべきなのか、考えてみることをおすすめします。

ポイント② 方向性の統一
コミュニケーションそのものに統一感が必要です。企業には存在理由があり、ビジョンがありますが、発信する情報が細かくなるほど、それが見落とされてしまう傾向があります。
組織が縦割りになると、ひとつのウェブサイト内でも統一感がなくなるケースがあります。さらに部署やコンテンツごとにバラバラに更新すると、企業の特徴や方向性が不明瞭になってしまいます。
広報担当者やウェブサイト担当者が企業戦略として目指すコミュニケーションを意識して指揮を執り、制作に関連する関係部署が横串で連携することで、企業の目指す方向性が統一されます。そうすることで、企業が「目指すもの」や「そのために注力している事業」などを、ターゲットに明確に伝えることができるようになります。
重要なのは一つ一つのコンテンツを更新することよりも、まずはウェブサイトの全体像を俯瞰してチェックし、ウェブサイト全体をマネジメントする視点を持つこと、その上でコンテンツを更新していくことです。
ポイント③ 情報を届ける工夫
企業が伝えたいこと”だけ”を伝えるウェブサイトでは不十分です。ターゲットが知りたい情報を意識した上で、企業が発信する情報をアレンジしなければ、単に情報が陳列された、カタログのようなウェブサイトになってしまいます。
外部のプラットフォーム、メディア、ステークホルダーへの広がりやファン化を意識して、「世の中が知りたい情報」と「企業が伝えたい情報」が重なるポイントを意識して設計し、発信することが重要です。
双方の目的が重なるポイントを作る「PR思考」を用いてウェブサイトを設計することで、ターゲットに届きやすい情報になるため、情報が浸透しやすく、広がりやファン化を起こしやすくなります。
まとめ
企業のコミュニケーションにとってウェブサイトは、「攻め」であり、「守り」でもあります。成果や数値を求める「攻め」も重要ですが、「守り」に意識を向けることも大事です。
読み手を意識した気遣いの確認、「守り」を固めるリスクチェックにしっかりと目を向けたうえで「攻め」を意識することで、より伝わるコミュニケーションが実現できるでしょう。
電通PRコンサルティングでは、使いやすさやSEO対策にとどまらない、ユーザーやメディアなど多様なステークホルダーが、”ポジティブな反応を起こす”ウェブサイトを実現するためのサポートをいたします。細や費用についてお知りになりたい方は、資料をダウンロードしてご確認ください。
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。
▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
▼伝えたい情報を的確に発信するための「PR思考のウェブサイト診断」メニュー資料をダウンロード
▼関連記事