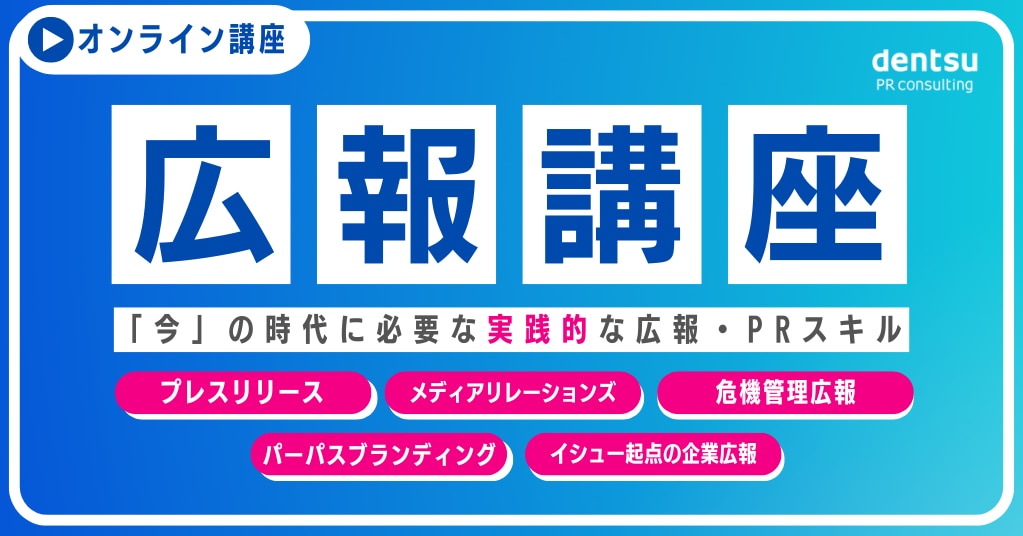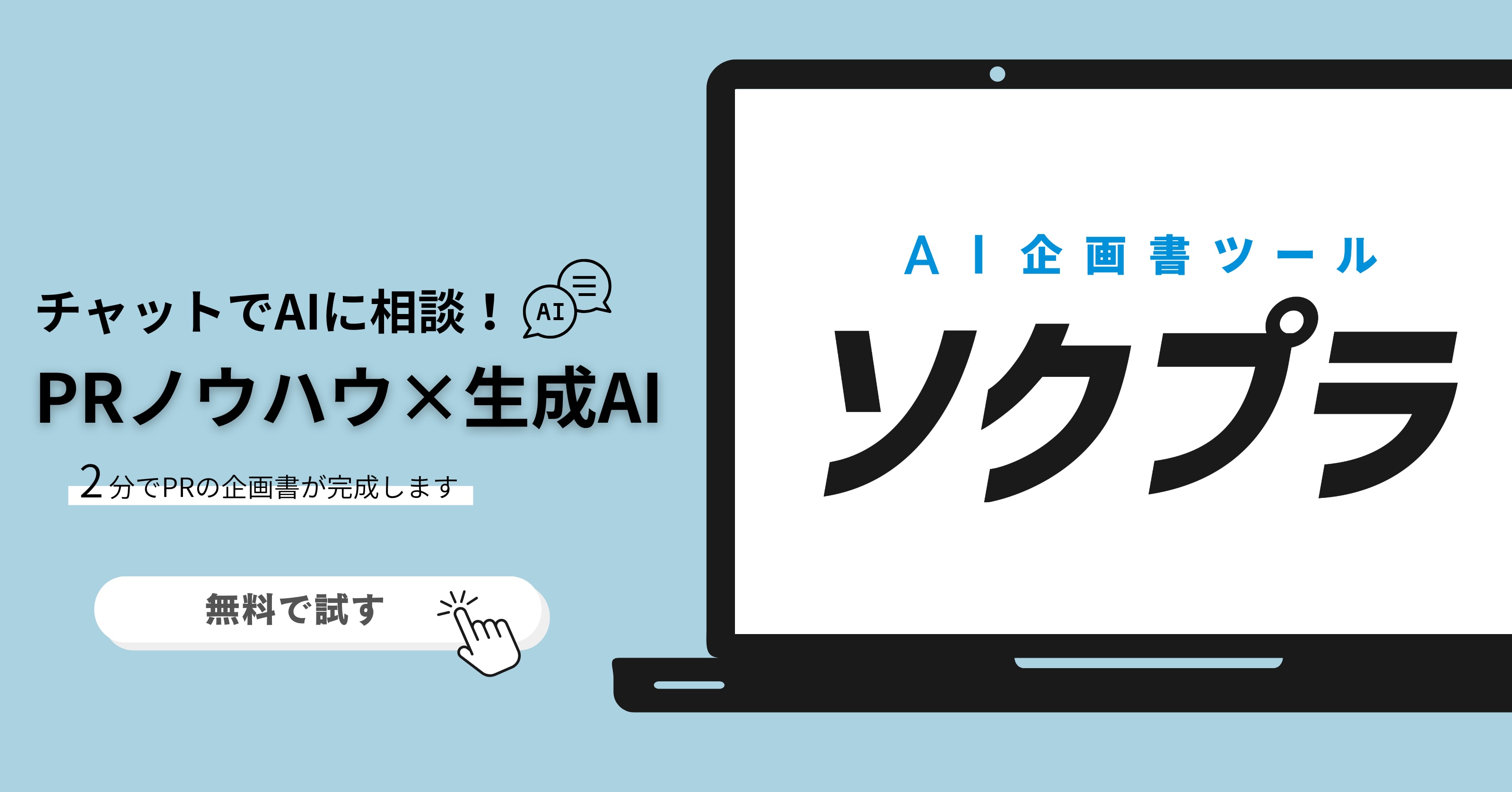デジタルPRとは?成功事例と戦略設計のポイントを解説
情報があふれ、生活者の関心が分散する今、従来型のPRやマーケティング戦略では対応できない課題が増えています。そこで注目されているのが、社会や個人のインサイトを起点にメディアやSNS、インフルエンサーなどを活用して設計する、デジタルPRです。
デジタルPRは、ターゲットの価値観や感情に寄り添い、デジタルを起点にしながらマスメディアやイベントなどのチャネルも横断して一貫したコミュニケーションを構築する発信手法。マーケティング、ブランディングやファン醸成まで、幅広い効果を発揮します。
本記事では、デジタルPRの基本的な考え方や設計のポイント、成功事例、そして電通PRコンサルティングが支援する具体的なアプローチまで解説します。
▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
目次[非表示]
デジタルPRとは?これまでのデジタル発信との違い

デジタル広告を出稿する。YouTubeで企業動画を発信する。オウンドメディアの更新に注力する。あるいは、インプレッション数やフォロワー数をKPIにしたSNSキャンペーンを実施する──。
こうしたデジタル上の発信は、マーケティングやブランディングを行う企業や団体にとって、日常的に行われている、有効な打ち手となっています。
ただし、こうした発信は、目の前のリーチ数やフォロワー数の増加に追われるばかりに、企業が本来、目指したかった施策の目標とは、懸け離れてしまうこともあります。
デジタルPRの目的は、インプレッションやリーチを広げることは大前提としつつも、その先にある、ターゲットの「意識」や「行動」の変化につなげることにあります。
例えば、ある商品をZ世代に広めたいとき、すでにデジタル広告などでリーチを獲得できていても、Z世代の中には「○○離れ」といった、商品ジャンルそのものへのマインドの壁が存在するケースもあります。
そこで、インフルエンサーと連携したイベントを企画し、“その商品ジャンルをどう楽しめるか”という体験を提供。参加したZ世代やインフルエンサーによって、イベントの様子がSNSをはじめとしてメディアで拡散され、商品全体へのポジティブな意識の変化を促し、購買行動へとつなげるようなアプロ―チを設計します。
このように、デジタルを起点にしながら、デジタル上の目の前の数字ではなく、本質的な課題に対してアプローチするのが、デジタルPRが本来目指すところです。
単発の施策ではなく、さまざまなデジタル上のメディアや、マスメディアやイベントなどのチャネルも横断して一貫したコミュニケーションを構築できるのも、デジタルPRの特徴です。
広報部・マーケティング部 それぞれから見たデジタルPR

広報部の視点に立つと、従来のプレスリリースやパブリシティ中心の広報活動では、「露出されるかどうか分からない」「一度の発表にかけるしかない」といった不確実性がつきものでした。SNSやWeb広告によるターゲティングを活用できるデジタルPRでは、これまでの広報活動を補完し、確実に情報を届けるルートを設計できる点でも注目されています。
広報活動の視野を広げ、メディア全体をPESOモデルの分類で捉えながら、デジタル広告などもうまく組み合わせて発信していくことが、今や広報部にとって自然であり、必須の取り組みともいえます。
一方、マーケティング部の視点に立っても、デジタルPRは有効に機能します。すでにデジタル広告などの発信に取り組んでいるが、「リーチ数をさらに伸ばしたい」といった悩みや「リーチの次にある本来の目標(ターゲットの認識や行動の変化)につなげることができていない」といった悩みもよく聞かれます。
特定のペルソナに対する「ワンメッセージ」「ワンビジュアル」といったシンプルな表現設計が重視される広告に対し、デジタルPRでは「マルチコンテクスト」の発想が求められます。情報を発信する際、メディアやインフルエンサー、生活者に向けた多様なストーリーや文脈を用意し、共感のきっかけを多層的に設計するアプローチが特徴です。
こうしたアプローチは、従来の運用施策だけでは届かなかった層にも情報を届け、企業の可能性を広げるものです。
従来のように「報道は広報部」「広告はマーケティング部」といった部門ごとの分業体制だけでは対応し切れない時代になってきており、両部門が連携しながら、戦略的に発信していく必要性が高まっています。
「リーチやインプレッションを増やしたい」「コンバージョンを取りたい」といった、明確な課題だけではなく、企業が抱える形の見えない課題に対して、さまざまな手法でプランニングができるのが、デジタルPRの強みといえます。
デジタルPRの全体構造と設計の考え方
デジタルPRに取り組む上で重要なのは、「一時的な話題化」や「単一チャネルでの露出」にとどまらず、世の中の価値観や課題意識と整合した発信と、チャネルを横断した一貫性を設計することです。
例えば、テレビCM前にSNS投稿が先行してしまうなどの情報齟齬は、ブランドの印象を損なうリスクにもなり得ます。トータルな情報設計と流通計画により、メディアごとの役割や順序を整理することが、目的達成の精度を高めるのです。

では、どのように個人や社会の文脈を捉え、情報を設計し、計画を立てればよいのでしょうか。ここからは、デジタルPRをプランニングするための基本構造と考え方を解説します。
“生活者の価値観”を可視化 「トライブ」の設計と分析方法
生活者の感情や関心は、属性だけでは語れません。そこで重要になるのが、「トライブ(=価値観でつながる生活者集団)」という単位です。
どんなイシュー(話題)が語られ、どんな集団がそこに共感しているのか。そこに向けた情報発信の設計が、共感と拡散の起点となります。

このイシューや共感を見つけるために、電通PRコンサルティングでは、SNS上の投稿や検索行動を基に、n=1単位での声を丁寧に拾い上げる個別分析アプローチ「ソーシャルハンティング」を活用しています。
▼関連記事
このプロセスでは、数値では捉え切れない生活者の文脈や関心の兆しを可視化し、トライブごとの“共通言語”を設計します。
そして、ここでの気付きを基にして、発信するコミュニケーションの核となるメッセージや、情報設計のプランニングが可能になります。
複数のメディアを組み合わせ 「PESOメディア設計」を意識
情報の設計や計画を立てていく上で重要なのが、PESO(Paid、Earned、Shared、Owned)モデルによってメディアを統合的に捉えたアプローチです。

単一チャネルで完結するのではなく、広告(Paid media)やSNS投稿(Shared media)、自社メディア(Owned media)、そしてメディア露出(Earned media)を戦略的に組み合わせることで、生活者に知ってもらい、行動を促します。
▼関連記事
例えば、策定したコアメッセージを基に、SNSで話題をつくりながら、それをニュースとしてメディアに展開し、自社のWebサイトやLPに呼び込んでコンバージョンを設計する…といった流れです。
ただし、商品やターゲットによって、最適な情報解禁タイミングやメディアの組み合わせは異なります。生活者やメディアの文脈を深く理解した上での設計がポイントとなります。
「マルチコンテクスト設計」で最適なプラットフォームを選定
生活者の情報接触や共感・拡散が起こる文脈は、プラットフォームごとに大きく異なります。
そのため、メッセージ発信においては「どの媒体で誰に届けるか」という視点で、内容や目的に応じたチャネルの選定が不可欠です。

全てのプラットフォームで同じ表現を使うのは非効率であり、各媒体における生活者の文脈や期待に合わせて、情報の切り口やトーンを調整する「マルチコンテクスト設計」によって、共感と拡散の精度は格段に高まります。
SNSの使い分け方を例に挙げると、Xでは共感と即時性、Instagramではビジュアル訴求、YouTubeではストーリー性が重視されるなど、特性に応じた最適化が重要です。
▼関連記事
デジタルPR 成功事例から見るポイント
ここでは、異なる業種における3つのデジタルPR施策を取り上げ、それぞれがどのような設計思想の下に共感を生み、成果につなげたのかを解説します。
若年層向けイベントでの拡散戦略(Z世代 × 体験設計)

Z世代向けの軽自動車の発売を記念し、新しいクルマの楽しみ方を提案するプロモーションイベントを実施。Z世代が憧れるインフルエンサーと共創し、Y2K・チル・おしゃピク・パーティーなどZ世代に親和性の高い4つの世界観で車両をプロデュース。会場では空間演出や撮影ブース、顔隠しアイテムなど、UGC(User Generated Content)を促進する仕掛けを多数展開しました。
SNS上では「楽しそう」「行きたかった」といった声とともに関連投稿が多く発生し、目標数を大幅に上回るリーチを獲得。イベントへも多くの人が来場し、インフルエンサーの共感力を生かした体験設計によって、話題化とブランド好意度の向上を実現しました。
▼事例ページ
観光PRアカウントの育成・共感型運用(TOKYO Besties)

「東京」の観光振興を担う団体のプロジェクトでは、東京在住の若者を起用し、SNSを通じて海外・国内双方へ東京の魅力を発信するPR隊「TOKYO Besties」公式アカウントを運用。タレントや芸能人ではなく、一般の若者をインフルエンサーへと育成するプログラムを構築しました。
SNS未経験者が大半である参加者に対し、人気クリエイターらによるワークショップや投稿添削を実施。投稿制作の基本から表現リスク、コンテンツの見せ方までを段階的に学習してもらうことで、自然体の発信力と自己表現力を高めました。
結果として、アカウントの成長とともに、PR隊の投稿クオリティも飛躍的に向上。「東京の魅力を知る・伝える」双方向の広報活動として、高い評価を得ました。
▼事例ページ
食品ブランドの共感型ブランド体験(meatful)

11月29日(いい肉の日・言いにくいことを言う日)に向けて、「いい肉を言い訳に、会話しよう」をキーメッセージに、YouTube、TikTok、Instagram、X(旧Twitter)でインフルエンサーによる「#MeatfulTime」体験を創出。
家族との団らんや自分へのご褒美といった“ごちそうシーン”を生活者が自然に投稿したくなる仕掛けとして設計しました。
インフルエンサーとのコラボ投稿やプレゼントキャンペーンを通じて、温かみや高揚感のあるブランド体験を拡張。ハッシュタグ活用やビジュアル統一によって、視覚的な世界観も醸成し、SNSでの共感・拡散を喚起しました。
▼事例ページ
いずれの事例も、ターゲットの共感を起点に、SNSやイベント、映像コンテンツなど多様な手法を組み合わせて文脈を設計し、生活者の行動変容へとつなげた、デジタルPRならではの事例といえます。
PR会社の支援体制とアプローチ
電通PRコンサルティングには、デジタルPRのトレンド研究やソリューション提案を行う専門チームがあります。
SNS、インフルエンサー活用、オウンドメディア、デジタル広告といった基本的な施策の支援をはじめ、戦略策定からコンテンツ制作、メディア設計、リスク管理までを一貫して視点できる体制を用意しています。そのため、企業が抱えるさまざまな課題に対して、幅広いソリューションによる提案が可能です。

電通PRコンサルティングのデジタルPR支援内容
以下に挙げる電通PRコンサルティングの特徴は、いずれも、デジタルPRの施策を設計する上で、重要な要素です。
▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
戦略設計:PESO全体を見据えた流通設計
メディア特性や目的に応じて、どのチャネルに、どの順番で、どのような形で情報を流すかを設計。認知から行動までのファネルを意識した流通戦略を描きます。
インサイト分析:ソーシャルハンティング×トライブ設計
n=1の声を拾う「ソーシャルハンティング」で生活者の隠れた関心事を発掘。ターゲットトライブに刺さる文脈と共感軸を導き出します。
文脈設計・マルチコンテクスト構築
生活者が「シェアしたくなる」情報とは何か?を軸に、プラットフォームに最適化されたメッセージやビジュアルを複数展開。SNS投稿からニュース露出までをシームレスに設計します。
コンテンツ制作力:企画から運用までの一貫体制
動画、SNS投稿、Web記事、OOH、イベント連動など、多様なアウトプットを実行可能。PR視点に立ったクリエイティブ開発と運用ノウハウが強みです。
リスク管理体制:表現・炎上対策も万全
デジタルPR施策においては、表現リスクの回避も重要です。メディアやSNSでの炎上対策、事前チェック体制、WOMJガイドライン準拠など、安全な実施を担保します。
独自メソッドの蓄積と再現性
電通グループ全体の事例を横断的に共有し、独自メソッドとして体系化。さまざまなフレームワークを活用し、担当者個人に依存しない、再現性のある支援を提供します。
まとめ|これからのデジタルPRに求められる視点
生活者の関心が細分化され、情報接触が多様化する中で、企業が「伝えたいこと」だけを発信しても届きにくくなっている昨今。生活者の感情や価値観に寄り添い、文脈に合った発信を設計することこそが、これからの広報やマーケティング活動に必要な視点です。
「うれしい」「しんどい」「応援したい」「知ってほしい」──
一人一人の感情が行き交うデジタルの世界で、電通PRコンサルティングは、その思いに寄り添いながら、共感を軸にした情報設計を支援しています。
今後さらに多様化・複雑化していく社会において、どのように「共感」を設計し、広げていくか。その戦略的視点と実践の積み重ねが、これからの企業の発信力を大きく左右します。
皆さんの広報・マーケティング活動において、デジタルPRをお役立ていただければ幸いです。
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。
▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
▼「n=1」分析の独自メソッド「ソーシャルハンティング」サービス紹介資料をダウンロード
▼「デジタルPR」について電通PRコンサルティングに無料相談する
▼関連記事
・【企業のSNS活用】始め方と選び方は?運用に大切な3つのこと