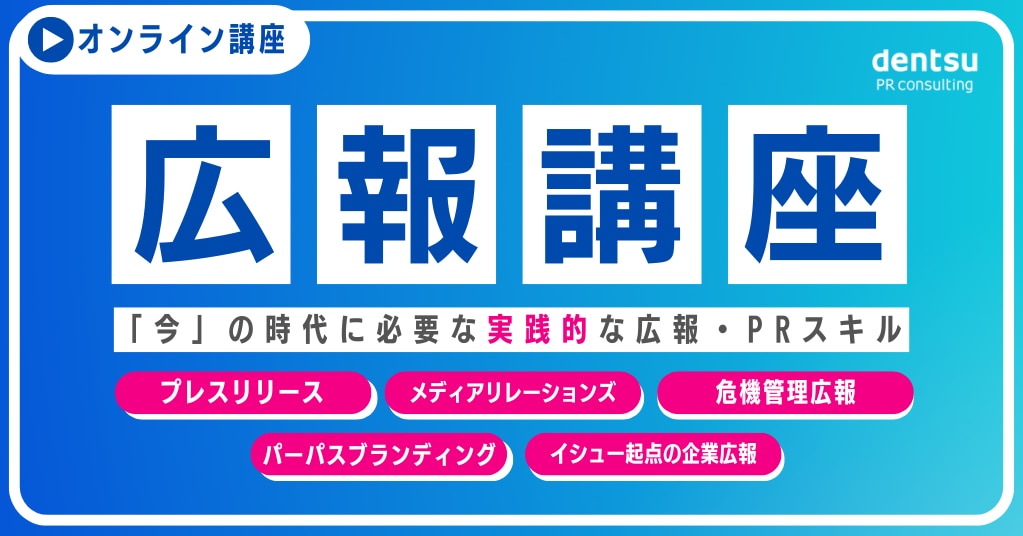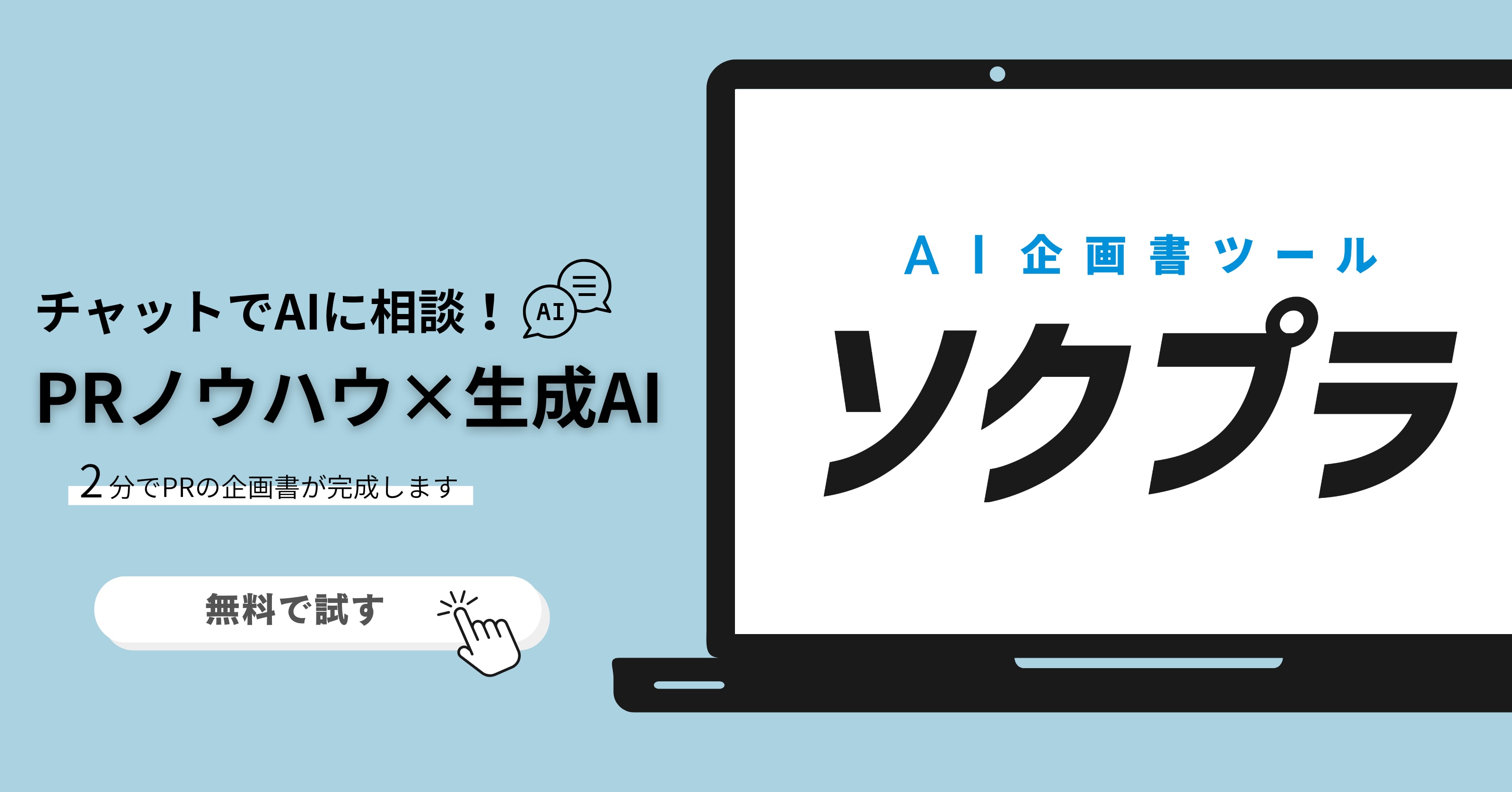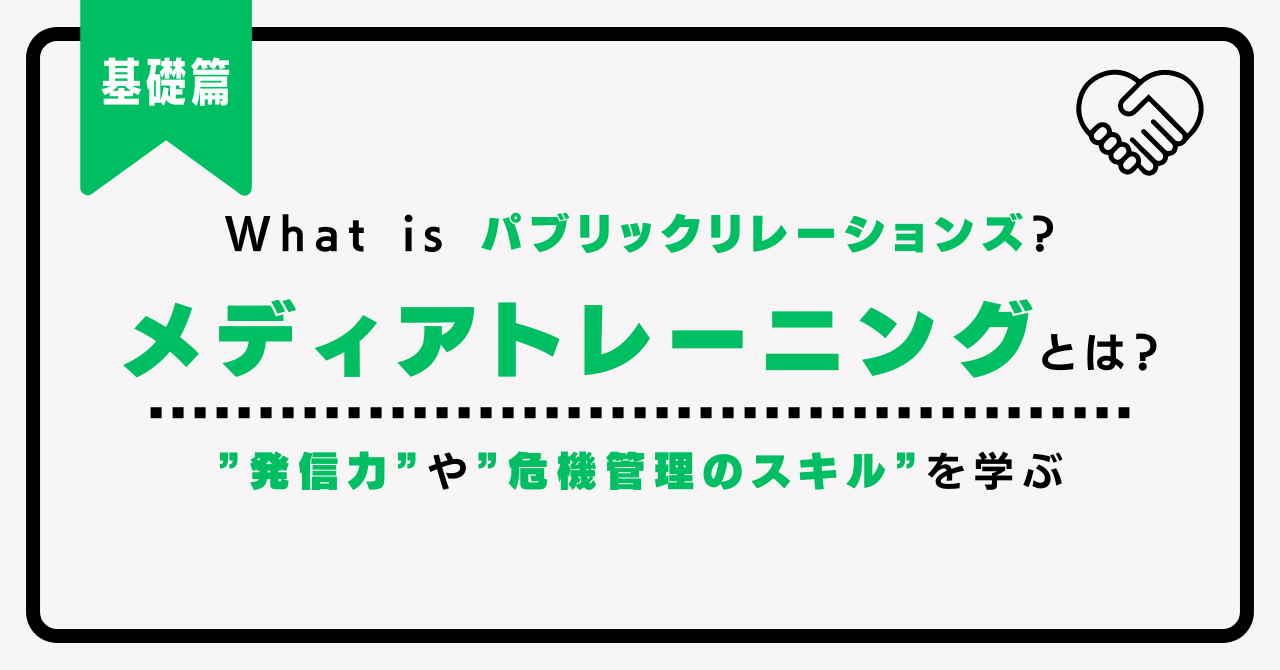
メディアトレーニング 研修の内容や参加時のポイントを詳しく解説
メディアを通じた企業の情報発信は、ステークホルダーに、企業のビジョンや価値を直接伝える貴重な機会となっています。企業広報としてはメディアを上手に利用して世の中に情報発信していきたいところですが、一方で、企業の危機ともいえる局面においては、トップの発言や行動が企業の命運を左右することもあります。
そこで重要になるのが「メディアトレーニング」です。メディアトレーニングを通じて発信力や危機管理のスキルを磨くことは、企業の持続的な成長に不可欠となりつつあります。
本記事では、メディアトレーニングの必要性、その具体的な内容、受講する際のポイントについて詳しく解説します。
▶電通PRコンサルティング「広報スキルアップのための研修プログラム」資料をダウンロード
▶“伝わり響く”社長発信をサポート「トップコミュニケーション・プログラム」メニュー資料をダウンロード
▶“不祥事”の影響を最小限に 「危機管理広報プログラム」メニュー資料をダウンロード
目次[非表示]
- 1.重要性が高まるメディアトレーニング
- 2.メディアトレーニング どんな種類がある?
- 2.1.広報セミナー
- 2.2.プレゼンテーショントレーニング
- 2.3.個別インタビュー取材トレーニング
- 2.4.緊急記者会見トレーニング
- 3.メディアトレーニング 研修の流れ
- 3.1.会場セッティング
- 3.2.模擬インタビュー取材の実施
- 3.3.振り返りと講評
- 4.メディアトレーニング 参加時のポイント
- 4.1.目的を明確に
- 4.2.シミュレーションは、よりリアルな環境で
- 4.3.フィードバックを自分のものにする
- 5.電通PRコンサルティングでは、多様なプログラムを提供
重要性が高まるメディアトレーニング
電通PRコンサルティングの社内シンクタンク「企業広報戦略研究所」が2023年に行った調査では、生活者が企業に対して魅力を感じる項目のランキングの上位にビジョンやリーダーシップに関する項目 が挙がりました。

さまざまな場面で日々発信されるトップメッセージは、各ステークホルダーとの良好な関係を築く上で、その重要性が一段と高まっていることが分かります。
また、SNSの登場により、企業の発信内容が瞬時に世界中に広がる一方で、炎上や誤解が生じるリスクも増大しています。企業は、迅速かつ適切な対応を求められる場面が増え、特にクライシス対応の重要性が高まっているといえるでしょう。
そのような中で有効な対策となるのが、メディアトレーニングです。
メディアトレーニングとは、企業の広報担当者や経営層が、メディア取材や記者会見などで効果的に対応するスキルを習得するための研修です。社長就任時にトレーニングを受けるケースはもちろんのこと、最近では役員や事業責任者などが「会社の顔」としてメディアに登場するタイミングで、事前にトレーニングを受けることも増えている印象です。
メディアトレーニング どんな種類がある?
メディアトレーニングには多様なプログラムがあり、それぞれの企業のニーズに応じて選択することができます。実際に、電通PRコンサルティングが提供するプログラムの一部を例に、研修内容をご紹介します。
広報セミナー
広報セミナーは、メディア対応の基本を学ぶためのプログラムです。
メディアと効果的にコミュニケーションを取るための基礎知識や、メディアの特性に応じた対応方法を学びます。
元記者やメディア事情に精通したコンサルタントから、メディア対応の基本知識(メディアの種類、広報活動におけるメディア)、取材対応時における心構え(メディアの関心事、NGワード、表現等)などのレクチャーを受けることで、取材を受ける準備や心構えを学ぶことができます。
プレゼンテーショントレーニング
企業トップは、社内外の多様なシーンでプレゼンテーションスキルが求められます。
特に株主総会や新事業発表などの記者会見には、分かりやすく、かつ説得力のある話し方が求められます。
トレーニングでは、レクチャーを受け自分のクセを知った上で、原稿を使いながらプレゼンテーションを実演。
講師とともにリハーサル映像を振り返りながら、視線の送り方、声のトーン、身ぶり手ぶりなど、重要なポイントについてアドバイスを受けることができます。
個別インタビュー取材トレーニング
このトレーニングでは、元記者やメディアの専門家が模擬記者として登場し、実際の取材を想定した質問に対応することで、インタビューの場での対応力を向上させます。
記者の関心事(本心)に答えつつも、“伝えたいメッセージ”を記事として掲載してもらう(見出しにする)ための応じ方を習得。メディアの特性やメディア対応の基礎知識などシミュレーションを交えて学ぶことができます。
緊急記者会見トレーニング
重大な事件・事故が発生し、緊急に記者会見する必要ができたという想定の下、テレビカメラやスチールカメラのカメラマンが出席する模擬記者会見場でおわびと状況説明を行い、その後、記者からの質問に答えます。
トレーニング後には、録画映像を見返しながら、フィードバックを受けることで、改善点を確認。記者会見時における基本動作や心構え、基礎知識全般が学べます。
メディアトレーニング 研修の流れ
電通PRコンサルティングの「個別インタビュー取材トレーニング」の流れを例に、メディアトレーニングの具体的な流れを詳しく見てみましょう。
会場セッティング
トレーニングは、まず会場の準備から始まります。インタビューや記者会見を想定したレイアウトにテーブルや椅子を配置し、必要な録画機材を設置します。
また、照明や音響の調整も行い、実際の記者会見に近い環境を再現します。
実際にこうしたセッティングを行ってもらうことにより、参加者はよりリアルな状況でトレーニングを受けることができ、実践に近い経験を積むことが可能です。
模擬インタビュー取材の実施
次に、模擬インタビューを行います。これは、実際のメディア対応を想定したリアルなトレーニングで、元記者やメディア事情に精通したコンサルタントが模擬記者として登場します。
インタビューでは、事前に設定されたテーマに基づいて質問が投げかけられますが、参加者には予測できない質問も含まれており、その場で即座に対応する力が試されます。
こうしたトレーニングを通じ、企業のメッセージを効果的に伝えるスキルを磨きます。また、この過程で、どのようにして企業のリスクを最小限に抑えつつ、ポジティブなメッセージを発信できるかを学べます。
振り返りと講評
インタビューが終わった後、参加者は録画された映像を見返しながら、講師からのフィードバックを受けます。ここでは、発言内容だけでなく、話し方や姿勢、アイコンタクト、声のトーンなど、非言語コミュニケーションの要素も含めて評価されます。
具体的な改善点が示されることで、参加者は自身の弱点を明確に認識し、次回以降の改善に役立てることができます。さらに、講師からは、どのようにすればインタビューがより効果的になるか、具体的なアドバイスが提供されます。
メディアトレーニング 参加時のポイント
効果的なメディアトレーニングのプログラムを選び、最大限に活用するためには、以下のポイントをしっかりと押さえることが重要です。
目的を明確に
トレーニングを受ける目的を明確にした上で、しっかりと「場面設定」をすることが、メディアトレーニングには重要です。
例えば、インタビュートレーニングを実施する場合は、どういう想定(どういう媒体から、何の目的で取材に来るのか)で行うかを定めることから準備を始めます。
危機対応を強化するためのトレーニングと、日常的なメディア対応力を向上させるためのトレーニングでは、内容や進め方が異なります。企業が抱える課題や目指すゴールに応じて、適切なトレーニングプログラムを選択することが必要です。
シミュレーションは、よりリアルな環境で
トレーニングの効果を高めるためには、実際のメディア対応を想定したリアルなシミュレーションが欠かせません。
電通PRコンサルティングのトレーニングでは、実際に模擬の記者がトレーニング対象者に取材をし、その様子をカメラで撮影します。
模擬の記者は、元記者やメディア事情に精通したコンサルタントが行うので、本番さながらの雰囲気で“模擬取材”を受けることが可能です。
フィードバックを自分のものにする
トレーニング後のフィードバックを活用し、改善点を明確にすることで、次回の対応に向けた具体的な改善策を講じることができます。
フィードバックは、ほとんどのケースで映像を見ながら行います。第三者の視点から自分の対応を振り返る貴重な機会であり、トレーニングの効果を最大化するために不可欠なプロセスです。
表現や言い回し、自身の話し方のクセなどメディア対応だけでなくコミュニケーションスキル向上につながる改善点に気付ける機会と捉えてください。
電通PRコンサルティングでは、多様なプログラムを提供
「取材を受けるだけなのにトレーニングなんて…」とちゅうちょする方もいるかもしれません。ただ、トレーニングで自身の姿を客観的に見るだけでも、その後の意識が変わってくることは間違いありません。
発信力が企業の今後を左右する時代。“本番さながら”の環境をつくることができる研修を通じ、メディア対応のスキルを向上させ、企業のブランド価値を高めましょう。
電通PRコンサルティングでは、さまざまなトレーニングプログラムを提供しており、企業のニーズに応じたカスタマイズが可能です。トレーニングへに関心をお持ちの方、受講希望の方は、ぜひ資料をダウンロードして詳細をご確認ください。
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。
▼電通PRコンサルティングの「広報研修プログラム」メニュー資料をダウンロード
▼“伝わり響く”社長発信をサポート「トップコミュニケーション・プログラム」メニュー資料をダウンロード
▼“不祥事”の影響を最小限に 「危機管理広報プログラム」メニュー資料をダウンロード
▼関連記事
・トップコミュニケーションで注意することは?元記者が解説する「3つのポイント」