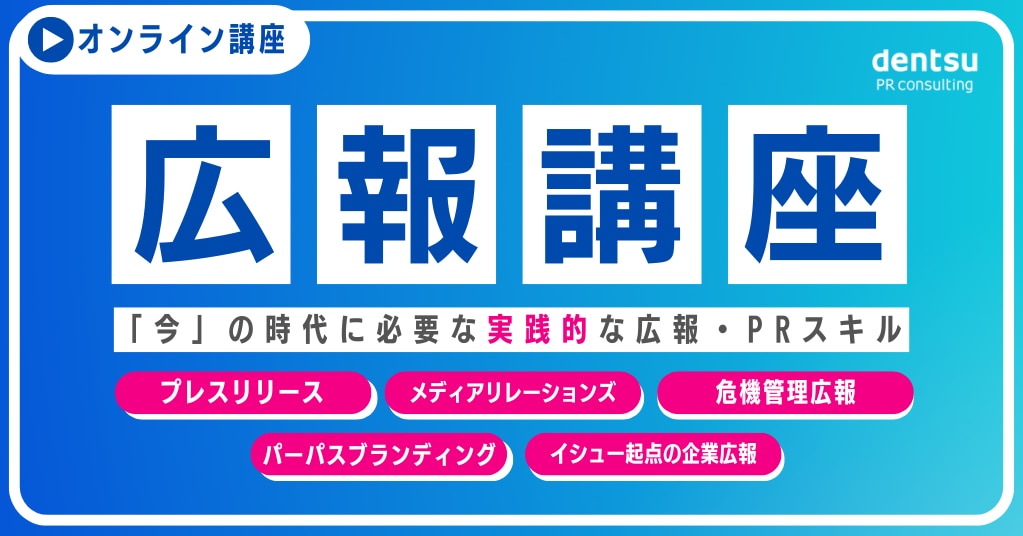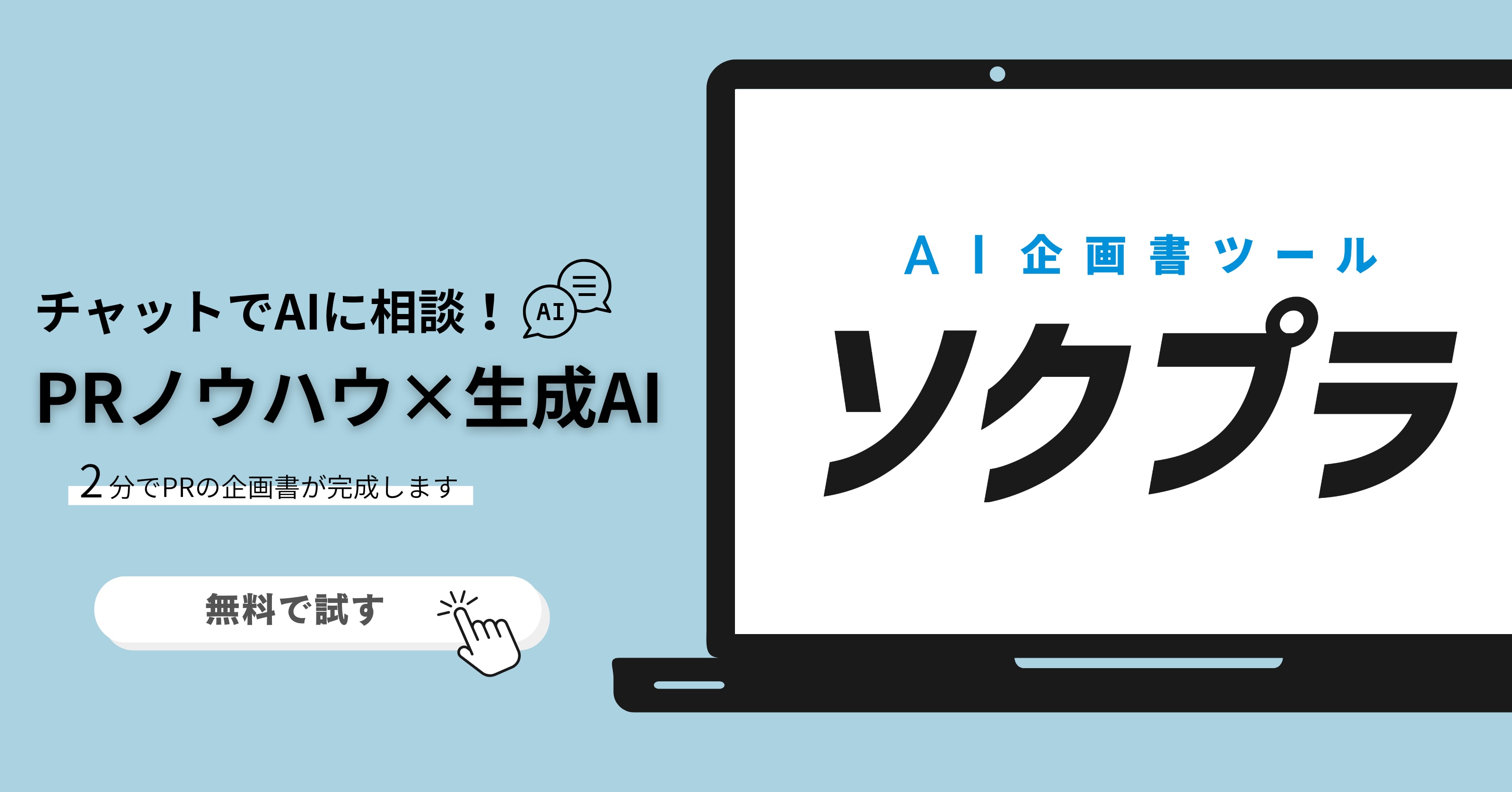ソーシャルリスクに強い企業のSNSアカウント運用とは -設計なき運用が生むSNS炎上について解説
企業やブランドの公式SNSアカウントは、いまや生活者とつながる重要な接点の1つとなっています。一方で、たった1つの投稿が批判や誤解の連鎖につながるケースも少なくありません。
SNSでのコミュニケーションを火種としたネガティブな反応を招かないために、企業は「ソーシャルリスク」にどのように向き合うべきなのでしょうか。
本記事では、企業にまつわるSNS炎上の火種を整理し、SNSアカウントの運用段階から重要となるコミュニケーション戦略の設計の在り方を考察します。
▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
目次[非表示]
企業を取り巻く「ソーシャルリスク」とは
日本パブリックリレーションズ協会は、ソーシャルリスクを、
「ステークホルダーがソーシャルメディア上に発信した情報をきっかけとして、情報漏えい、風評被害、名誉毀損、反社会的な行為や犯罪行為の露呈などが複合的に発生し、当該企業に対して信用失墜、取引停止や企業価値の低下など致命的なダメージを与えるリスク」
と定義しています(引用元より一部省略:https://prsj.or.jp/dictionary/ソーシャルリスク(social-risks))。
SNSが企業と生活者を直接つなぐいま、こうしたリスク対応はもはや一過性のトラブルではなく、コミュニケーション戦略そのものの設計力が問われています。
SNSの特性とメリットの裏にあるリスクを理解する
企業が情報を発信する主な目的は、ステークホルダーとの良好な関係構築です。
不特定多数のユーザーが存在するSNSでは、コミュニケーションをとりたいステークホルダー以外とも容易に接点をつくることができるため、意図していないネガティブな情報拡散が生まれやすいコミュニケーションの場でもあります。
また、他のコミュニケーションツールと比較すると、大きな費用をかけなくても手軽に情報発信ができるという特性もあり、体制やレギュレーションなどをきちんと策定しないまま運用を始めるという企業もあるでしょう。
しかしその場合、運用担当者の常識や感覚に頼って運用することが多くなり、その結果、例えば、投稿文の副助詞の用法一つで炎上するといったことも起こり得るのです。
SNS炎上を生む社会的背景と企業側の課題
相次ぐSNS炎上の背景には、社会的価値観の変化があります。働き方や子育て、ジェンダー規範の固定観念からの解放など、ここ数年社会は目まぐるしく変わり、「新しい価値観」を社会全体で創り上げる流れにあるいま、企業にもその姿勢が求められています。
SNSの投稿でいわゆる「古い価値観」が露呈してしまったり、時代と逆行した姿勢と受け止められると、批判につながっていきます。
一方で、万人に好かれる姿勢をとるのは難しいことも事実です。
過度に炎上を恐れ “八方美人”になるのではなく、自社にとって重要なステークホルダーの優先順位を定め、その人たちにとって有用な姿勢・情報発信を行うことが、信頼構築の第一歩です。
企業にまつわるSNS炎上の火種とは
「炎上」は、インターネット上での特定の対象に対して批判が集中しネガティブな文脈で拡散され、沈静化が困難な状態を指しますが、企業のSNS炎上には主に2つの火種があります。
1つは一般ユーザーの投稿が発信源となる場合、もう1つは企業公式SNSの投稿が発信源となる場合です。いずれの場合もSNS上で相互に影響し合い、連鎖的に拡散することに変わりなく影響が増幅されていきます。
【一般ユーザー発】企業によるオフラインでの行為・発信が要因
企業やブランドの事業活動による行為や対応が、一般ユーザーの投稿などを通してSNS上で拡散されるケースです。製品リコールや従業員の接客態度、労務問題、広告に起用したタレントの不祥事など、現実での出来事が「不誠実」と受け止められ、動画やコメントとともに炎上へ発展する例があります。
経営姿勢や組織文化に根差すケースが多く、経営体制全体のリスクマネジメント領域に関わります。
【企業公式SNS発】SNS投稿そのものが要因
企業やブランドの公式SNSアカウントによる投稿内容やキャンペーン企画が、SNS上で批判や議論を呼んで拡散されるケースです。差別的・過度な表現、社会的文脈への配慮不足、誤解を招く演出などがきっかけとなることがあります。
投稿1つが瞬時に広がり、経営活動を脅かすリスクを含んでいますが、SNS運用の中で日常的に生じる可能性があるもので、事前の戦略設計やチェック体制などによって未然に防ぐことが可能なリスクでもあります。
ソーシャルリスクに強い戦略設計に重要な3つのポイント
SNSのアカウント取得は手軽にできる一方で、運用は決して即日で始めるべきものではありません。
どんな目的で、誰に、どのような情報を届けるのかを事前に整理して、準備検討を丁寧に行うプロセスこそがソーシャルリスクに強いコミュニケーション戦略の設計につながります。
その戦略を立案する上で、重要なポイントは主に3つあります。
目的の明確化
いわゆる「バズること」を目的に据えず、「SNSを通してどんなコミュニケーションを築きたいか」をまずは考えていくことが大切です。
企業の発信をきっかけに、ポジティブな情報拡散が起きるプロセスで「ああ、この会社、いいな」「頼もしいな」「かわいいな」「かっこいいな」などと思ってもらうことができれば、その結果として、モノが売れる、株価が上がる、求人応募が増えるなどのことにつながって、よい循環が生まれます。
「バズ」らなくても、大切にしたいステークホルダーと関係を築くことはできますし、対話をすることも可能です。
どんな人にどう思ってほしいか、そのためにどんな公式SNSでの発信にする必要があるのかをPR思考によって最初に定めることで、企業公式アカウントが過激な投稿やターゲットを蔑ろにする投稿を避けることができるようになります。
体制を整える
企業の規模などにより異なりますが、SNS運用は基本的には複数人で管理できる体制を整えた方が良いでしょう。特に投稿内容と日時の確認は、2人以上で実施することをお勧めします。
複数人で管理できる体制を整えておけば、担当者が異動や退社をしたとしても、そのアカウントが問題なく継続する状態をつくることができます。また、1人の視点や感覚だと見落としやすい表現や内容だったとしても、複数人で確認すれば投稿する前に修正できる可能性が高まります。
この体制づくりが、再現性の担保とリスクを未然に防ぐことにつながります。
また、万が一、何か起こってしまった時に誰がどう動くのか、連絡系統などを含めたマニュアルやガイドラインを整備し、平時と緊急時の体制を整えましょう。
その企業やブランドが発信する“必然性”を考える
企業やブランドが発信する情報には、「なぜ自分たちがそれを語るのか」という“必然性”が求められます。
自社の社会的な存在意義やブランドの方向性と整合した内容を届けること、等身大でありながら、一貫したキャラクター設定とメッセージを保つことが、信頼を積み重ねる基盤となります。
この必然性が伝わる設計ができていれば、たとえSNS投稿に多少の毒気や尖りがあっても、生活者からは「この企業なら理解できる」と受け止められるのです。
つまり、トンマナや表現の強弱ではなく、「何を」「誰が」「なぜ」伝えるのかという一貫性こそが、炎上を防ぎながら共感を生む要となります。
企業SNS炎上の想定事例分析―謝罪、説明、沈黙―
投稿が炎上してしまった場合、企業は対応を迫られます。
一方で、SNS炎上を引き起こしている人たちが、あくまで生活者の一部であることにも配慮しなければいけません。
企業側も誠実かつ毅然とした姿勢で、炎上という事態とステークホルダーに向き合うならば、謝罪一辺倒ではない説明を発信したり、反対に意図的に沈黙を貫く姿勢をとることを考えても良いでしょう。
戦略を現場で生かすために―SNS運用担当者や広報・PRが持つべき視点―
SNS運用や広報・PRの現場では、投稿すること自体がゴールではありません。
投稿の先にどんな社会の空気やステークホルダーの反応が生まれるのかを観察し、その反応を踏まえて次の発信を設計していく――この地道なサイクルの積み重ねによって、良好な信頼関係の構築につなげていくものなのです。
AIをはじめ、新たなプラットフォームや技術の登場など、環境の変化は今後も続きます。デジタル環境と社会情勢は常にソーシャルリスクと隣り合わせである一方、そこには新たな発信の可能性も広がっています。
過剰に反応することなく、変化の先にどんな人たちがいるのかを想像しながら、発信の在り方を考え続けていかなければなりません。
言葉の使われ方も画像やイラストが示唆する意味も、時代やタイミングで変化します。
日常の運用段階から体制を整え、炎上事例があればニュースに目を通し、感覚と常識をアップデートしながらコミュニケーション戦略を定期的に見直していくことが、ソーシャルリスクに強い企業をつくるでしょう。
電通PRコンサルティングでは、体制づくりをはじめ、アカウント運用マニュアルの作成や運用コンサルティング、ソーシャルリスクの勉強会の開催など、運用の前段階から運用中の伴走までを得意としています。リスクを極力低減しながら、ステークホルダーとの良好な関係をSNSを通じて構築していきたいときは、ぜひ一度当社にお問い合わせください。
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。
▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
▼「n=1」分析の独自メソッド「ソーシャルハンティング」サービス紹介資料をダウンロード
▼「SNS運用」について電通PRコンサルティングに無料相談する
▼関連記事
・【企業のSNS活用】始め方と選び方は?運用に大切な3つのこと