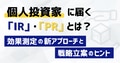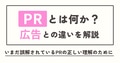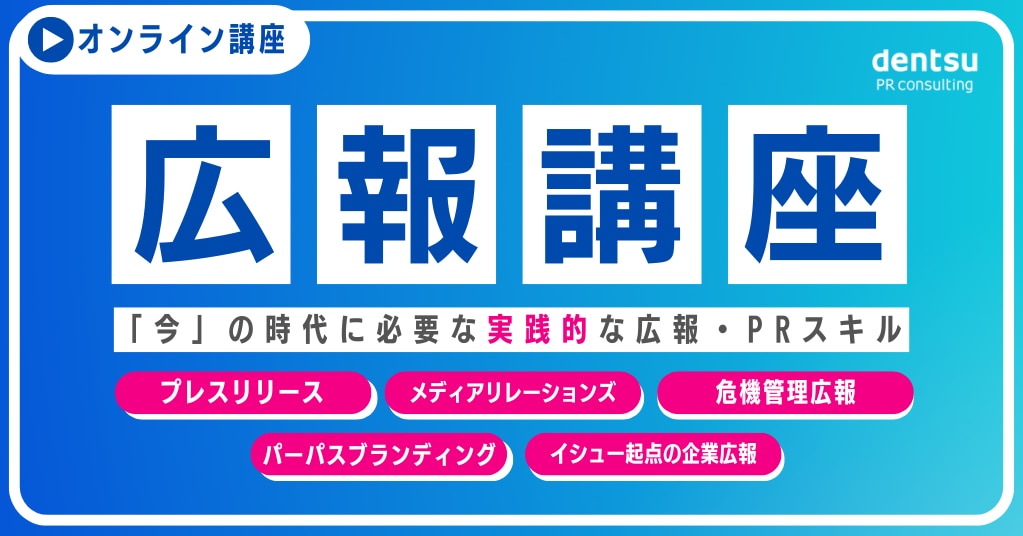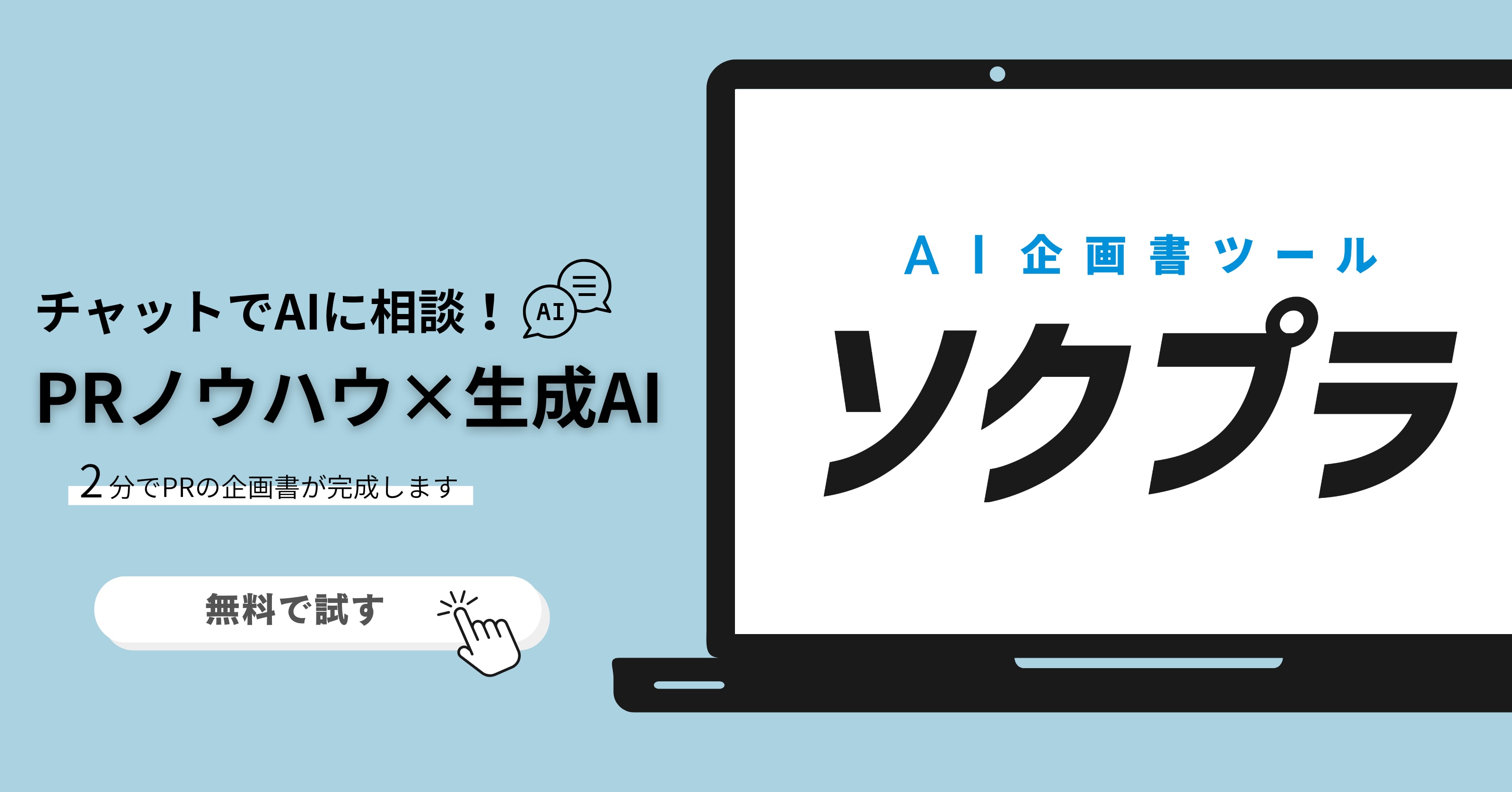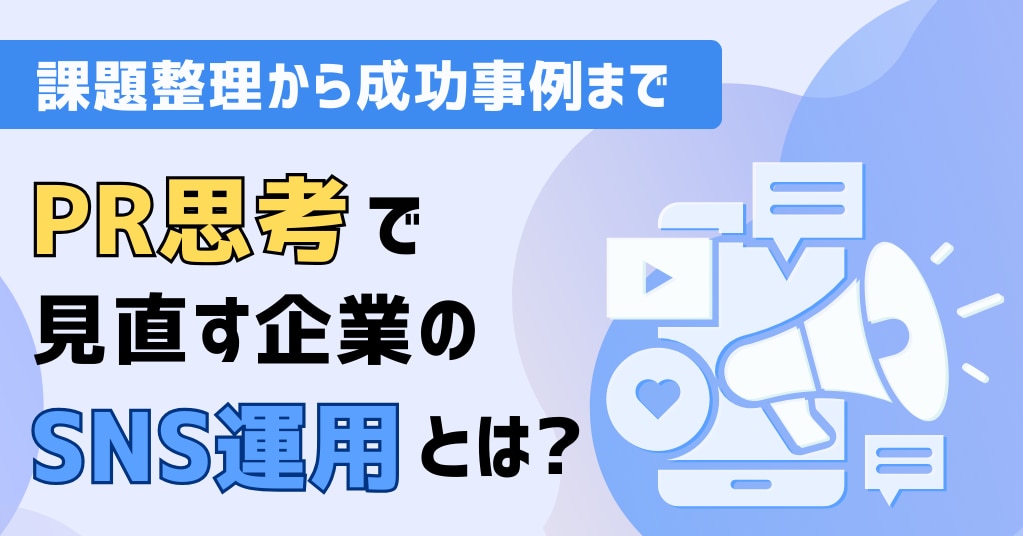
課題整理から成功事例まで──PR思考で見直す企業SNS運用とは
企業やブランドが、オウンドメディアの一つとして公式SNSアカウントを活用した情報発信を行う動きは、年々広がりを見せています。
帝国データバンクの2023年の調査によれば、40.8%の企業がSNSを活用しています(※1)。SNSは情報発信にとどまらず、顧客や生活者との接点として、ブランドや企業の信頼構築にも関わる重要なチャネルとなっています。
本記事では、X、Instagram、TikTokなど、企業やブランドの公式アカウントとして活用が進む主要なSNSを中心に、その運用において現場が抱える課題を整理し、PR思考で運用している企業の成功事例とその共通点について解説します。
※1 出典:帝国データバンク「企業におけるSNSのビジネス活用動向アンケート」(2023年9月)
https://www.tdb.co.jp/report/economic/xhldw9cakj/
※本稿ではソーシャルメディア全般を便宜上「SNS」と表記しています。
▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
目次[非表示]
- 1.広がる企業のSNS活用──ファンや顧客と直接つながれるのが魅力
- 2.企業SNS運用に多い課題と解決策──背景と改善ステップ
- 3.PR思考で見直す、SNS運用の軸となる企業やブランドの“ありたい姿”とは
- 4.【成功事例3選】PR思考×SNS運用で成果を出す企業の共通点とは?
- 4.1.事例①ヘルスケア企業──XとInstagramでファンと共に社会課題に寄り添う
- 4.2.事例②ホビー系ブランド──TikTokのショート動画で新規顧客を開拓
- 4.3.事例③家電ブランド──XとInstagramのSNSキャンペーンで共創を実現
- 5.企業SNS運用の現場に潜むリスクと対策──権利・炎上・投稿モーメント
- 6.トレンドに流され過ぎない企業SNS運用のすすめ
広がる企業のSNS活用──ファンや顧客と直接つながれるのが魅力
若者中心のコミュニケーションツールとして広まったSNSは、いまやあらゆる年代に浸透し、企業活動においても欠かせない情報発信の場となっています。BtoC企業では、商品の認知拡大や販売促進、BtoB企業では採用や企業認知の向上、ブランディングなど、目的に応じた活用が広がっています。
SNSの最大の特徴は、ファンや顧客と直接つながれることです。企業の規模や業種を問わず、その重要性は年々高まっています。
企業SNS運用に多い課題と解決策──背景と改善ステップ
企業SNSの運用を続けていくと、現場では多くの課題に直面します。運用体制の面では、リソース不足やアカウント運用の属人化などがあります。また体制が整っていても、アカウントを成長させるには、トレンドや文脈を押さえ、休まず継続的に情報を発信し続けていく必要があります。
企業SNS運用の現場で“ありがち”な課題
“とりあえず開設”してみたアカウントがある
休眠状態のアカウントがある
運用マニュアルが存在しない
アカウントの役割や目的が運用していくうちに曖昧になった/見える化されていない
さまざまな部署からばらばらに情報発信を求められ、運用方針がブレている
店舗やブランドごとにアカウントがあり、アカウント間の動きが連携されていない
こうした課題の背景には、SNSアカウントの“立ち上げやすさ”があるかもしれません。自社でアカウントを開設する行為自体には多大な費用はかからないためです。それ故に、目的が曖昧なまま運用が始まり、方向性を見失うケースが少なくありません。
これらの課題を解消するには、
アカウントの目的・役割の明確化
運用体制を整理し、属人化を防止
各SNSのアルゴリズムや仕様を理解した上での発信戦略・コンテンツ設計
などといった、中長期的な視点での運用設計がアカウント開設時から必要となります。さらに、定期的な運用状況の振り返りやKPIの見直しを行うことで、PDCAサイクルに乗せやすくなります。
まずは、企業SNSを通じて顧客や製品のファンなどのステークホルダーとどんな関係を築きたいのかを再確認し、その目的と戦略を明確化しましょう。その上で適切な人数の担当人員の配置や危機発生時の緊急フローを整備、マニュアル化し、関わるスタッフの意識を統一します。こうして整えた体制と戦略に基づき継続的に発信することで、SNSアカウントの効果を最大化できます。
PR思考で見直す、SNS運用の軸となる企業やブランドの“ありたい姿”とは
SNS運用をしていると、「もっとフォロワーを増やしたい」「バズらせたい」といった目先の目標が先行してしまいがちです。しかし、こうした数値や盛り上がりは、短期間に結果が見えやすい半面、ユーザーの反応が一過性にとどまり、企業やブランドとの継続的なエンゲージメントには結びつかない場合も少なくありません。SNSアカウントの運用で果たすべき本来の目的からアカウントの姿が乖離(かいり)してしまう理由の一つです。
そうなってしまった際に一度立ち止まって考えたいのは、企業やブランドとしての“ありたい姿”です。SNSアカウントを通して、何が伝わればいいのか、ファンや顧客とどんな関係を築いていきたいのか――そうした視点から逆算することで、目的が明確化していきます。これが社会と企業をつなぐ「PR思考」を取り入れたSNS運用の在り方です。
私たちが企業のSNSの運用支援を始める際には、まずこの原点に立ち返る作業を一緒に行います。例えば1時間のヒアリングの中で、冒頭と終わりで運用目的がまったく別の方向に変わることさえあります。
「誰に」「何を」「どう伝えるか」を文脈から再設定した企業SNS運用の軸が定まると、運用チーム内での共通認識が生まれ、判断やコンテンツ制作の基準がブレにくくなります。こうして蓄積された一貫性のある情報発信が、企業やブランド価値の向上にもつながります。
【成功事例3選】PR思考×SNS運用で成果を出す企業の共通点とは?
SNSは、企業とファンや顧客の身近な接点となるツールです。そのため、そのファンや顧客の関心ゴトと社会の関心ゴトに、自分たちが伝えたい情報をうまく掛け合わせて発信する必要があります。
そんなPR思考を取り入れたSNS運用に成功している企業の共通点には、以下が挙げられます。
- 伝えたい情報に応じたプラットフォームの使い分け
- 各SNSのアルゴリズムや仕様を踏まえたコンテンツ設計
- 他施策と連動した情報の流れを設計・発信
こうした共通点を踏まえたSNS運用を実践し、成果を上げている企業の事例を紹介します。
事例①ヘルスケア企業──XとInstagramでファンと共に社会課題に寄り添う
大手ヘルスケア企業は、5年間にわたり、女性特有の生活課題と向き合う啓発プロジェクトを展開。Xはプロジェクト立ち上げ当初に開設し、拡散力を生かした情報発信を継続。
一方で、主なターゲット層である20~30代の女性がアクティブユーザーであるSNSプラットフォームでも並行して運用していきたいという考えから、1年前よりInstagramでも新規アカウントを開設しました。
ビジュアル特化のコンテンツが好まれるInstagramでは、難しい調査データやリアルイベントの様子などをビジュアルで理解しやすく表現した静止画やストーリーズ向け動画を制作。 社会的にセンシティブなテーマを扱っていることからも、全方位的な情報発信ではなく、ファン/フォロワーに寄り添うことを第一に考えた運用を行っています。
フォロワー数(量)よりもフォロワーとの関係性(質)を重視し、両SNSの特性を生かすことで、テーマの社会的認知拡大とファンとの関係づくりを実現している好事例です。
事例②ホビー系ブランド──TikTokのショート動画で新規顧客を開拓
大手ホビー系ブランドは、複数のSNSプラットフォームを運用する中で、周年事業の一環として3年前にTikTok運用を開始。同社商品は、市場シェアに強みはある一方で、生活者からのブランド名認知が低いという課題がありました。
そこで、既存ファン/フォロワーとの関係構築を担うInstagramやXではなく、TikTokでライト層へのリーチを目指すこととし、既存ファン以外のユーザーにも一目で魅力が伝わりやすい商品を選定し、ブランド名と併せた発信を重ねています。
その結果、ブランドと商品を紐づけた認知が進み、TikTok経由でブランドを知る新規層が増加。フォロワー数も順調に伸長しました。新規ユーザーにリーチしやすいTikTokの特性を最大限に生かした運用を実現した事例の一つです。
事例③家電ブランド──XとInstagramのSNSキャンペーンで共創を実現
大手家電ブランドは、春の新生活期に向けたブランディング施策として、「人々の心に残る記憶や音楽」を起点にしたSNSキャンペーンを実施。
既存のXおよびInstagramアカウントを活用し、約1カ月かけてユーザーから思い出の写真や音楽、エピソードを募集。寄せられた投稿を広告やノベルティとして展開する広告連動型企画として、インフルエンサーとのタイアップ施策も同時期に展開しました。
思い出の写真とそれにまつわるエピソードを組み合わせた投稿は、ビジュアルをメインとするInstagramとの親和性に加え、テキストがメインであるXでも拡散されやすく、多数の応募が集まりました。
さらに、ユーザーが自身の投稿が広告になった現場に足を運び、その広告を撮影した写真を再びSNSに投稿するという二次拡散にもつながりました。
短期間ながら、ブランドの思いや世界観を生活者と共創した事例といえます。
企業SNS運用の現場に潜むリスクと対策──権利・炎上・投稿モーメント
成功事例の裏側では、実は地道なリスク管理や事前準備が行われています。SNSは即時性と拡散力が魅力ですが、その特性故に小さな見落としが社会的信用を失うトラブルに発展することもあります。ここでは、現場で起こりやすい3つのリスクと対応策を紹介します。
- 炎上を防ぐための表現と事前チェック体制を整える企業のSNS運用ルールをまとめたSNS運用マニュアルには、「発信しない」判断基準や炎上時の対応フローについても明記します。専門家も含めた複数の目で事前チェックを行うことで、攻めと守りのバランスが取れた発信が可能になります。投稿テキストや画像はもちろん、絵文字表現一つにしても無意識に差別的な意味を持たないかを吟味し、運用チーム内でも共通認識を持った上で複数人の目を通した事前チェックを徹底しましょう。
- 投稿モーメントを見極め、配慮して発信する関係者が多いと、情報の発信タイミング=投稿モーメントへの配慮が抜け落ちることがあります。例えば、企業やブランドから新発表をする日は、歴史的に意味を持つ日を避けて設定するなど、慎重な判断が必要です。発売日など、日付を変更することが難しい場合には、発信を前倒しするなどして、その日は発信を控えるといった対応も有効です。
- 写真や音楽などの権利処理の抜け漏れを防ぐ自社制作ではない素材を使用する場合、撮影者や著作者の許諾、被写体となる施設やイベント主催の掲載許可も必要となるケースがあります。例えば、SNS上にアップされている音源であっても、企業公式アカウントが使用する場合は権利者への申請が必要な場合が大半です。また、フリー素材サイトからの素材の使用なども、必ず利用可能範囲に該当しているかの確認を行ってから規定に沿って使用するなど、権利確認や事実確認をセットで行うことで、クリーンで信頼されるアカウントに成長していきます。
トレンドに流され過ぎない企業SNS運用のすすめ
SNSの世界では、時流に乗った発信が大きな反響を呼ぶこともあります。しかし、企業にとって重要なのは、短期的な注目だけではありません。むしろ、自社の“ありたい姿”を軸に、ファンや顧客との関係を着実に築いていくことが欠かせません。
こうして“ありたい姿”から逆算して設計されたSNS運用は、フォロワー数や一時的な反響にとどまらず、ブランドに対する信頼や好意といった中長期の資産を育てていきます。トレンドに必要以上に依存せず、常にその企業・ブランドらしい発信を続けることが、結果的にファンとのエンゲージメントを高めることにつながるのです。
SNSの運用を始めたいけどどのプラットフォームが適しているのかわからない、マニュアルを作りたいが知見がない、他の情報発信と連動したSNS運用はどうすればいいなど、SNS運用でお困りごとがありましたら、ぜひ電通PRコンサルティングまでご相談ください。
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。
▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード
▼「n=1」分析の独自メソッド「ソーシャルハンティング」サービス紹介資料をダウンロード
▼「SNS運用」について電通PRコンサルティングに無料相談する
▼関連記事
・「オウンドメディアとは」から考える、PR視点で成果を出すオウンドメディア戦略