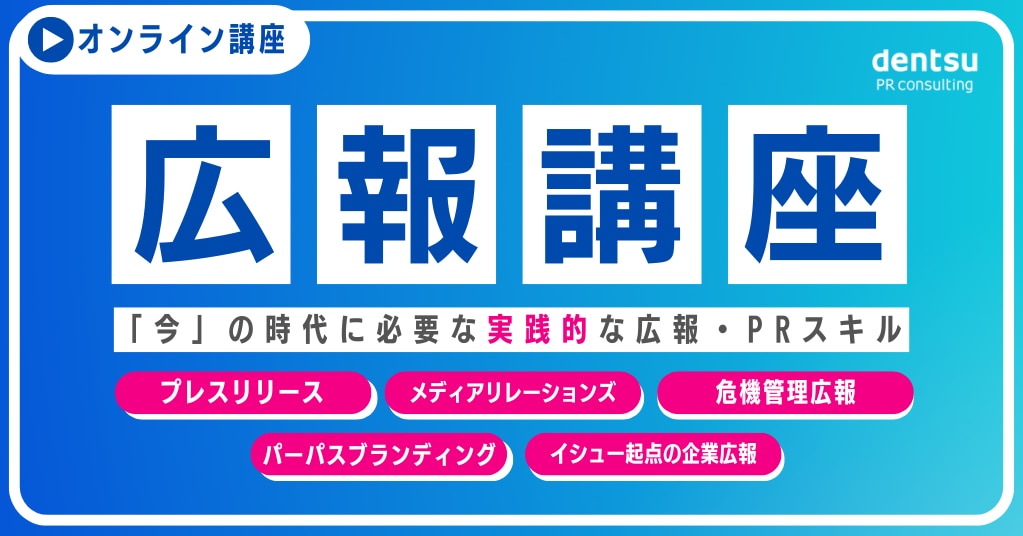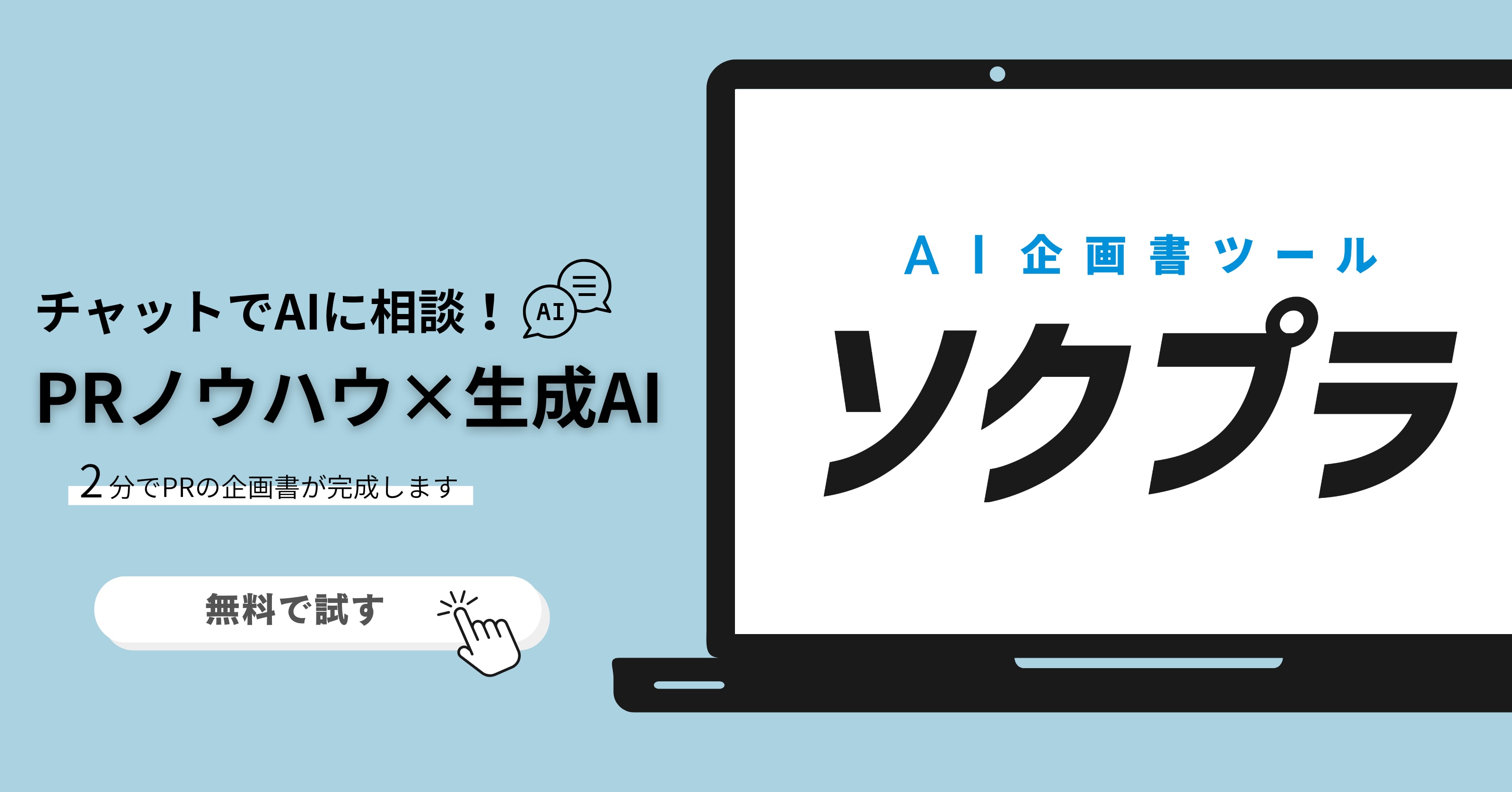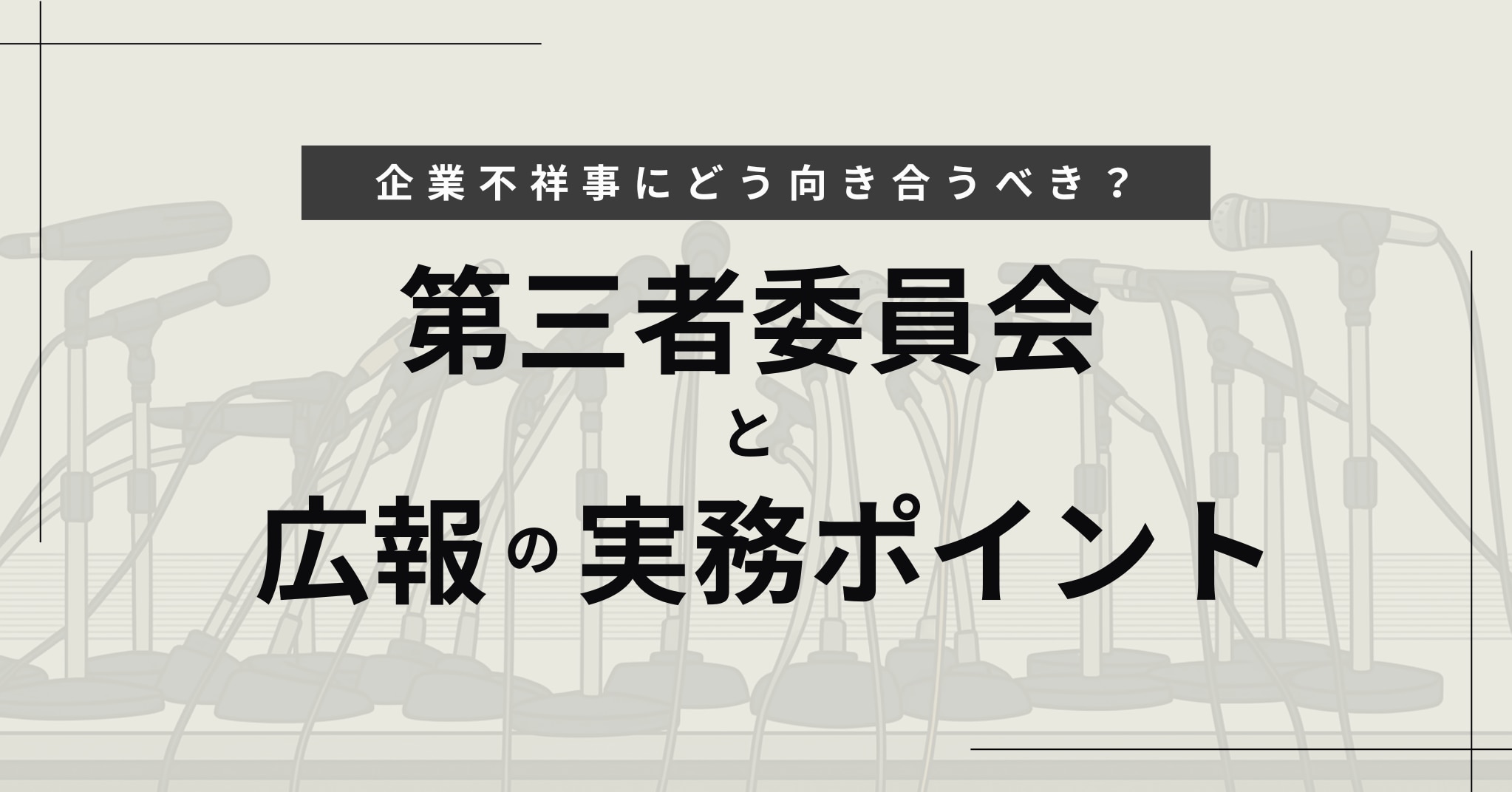
企業不祥事にどう向き合うべきか?第三者委員会と広報の実務ポイントを弁護士が解説
企業不祥事が起きたとき、調査委員会の設置や記者会見の対応をどう進めるべきか――。
その判断は、企業の信頼回復に直結する極めて重要な経営課題です。
本記事では、数多くの第三者委員会で委員長・委員を歴任し、企業法務・ガバナンスの第一人者である中村直人弁護士に、調査委員会の種類と使い分け、ガイドラインの運用課題、再発防止策の実効性、そして広報担当者が担うべき役割について伺いました。
理想論ではなく、数々の現場を知る弁護士だからこそ語れる“実務の本質”に迫ります。

中村 直人(なかむら なおと) 弁護士
1982年司法試験合格、83年一橋大法卒。85年森綜合法律事務所(現森・浜田松本法律事務所)所属。98年久保利英明弁護士らとともに日比谷パーク法律事務所開設。03年中村直人法律事務所(現中村・角田・松本法律事務所)を開設して独立。23年4月、中村法律事務所開設。
会社法やガバナンス、コンプライアンスが専門。企業へのコンサルティングや訴訟支援、第三者委員会の委員長、委員などの経験多数。
日本経済新聞の「企業が選ぶ弁護士ランキング」において、2021年まで10年連続で総合首位だった「レジェンド」弁護士。
▼関連記事
▶“不祥事”の影響を最小限に 「危機管理広報プログラム」メニュー資料をダウンロード
▶“伝わり響く”社長発信をサポート「トップコミュニケーション・プログラム」メニュー資料をダウンロード
▶“その表現、大丈夫?”発信前に確認できる「感情リスクチェックシート」をダウンロード
第三者委員会 vs 社内調査委員会:設置の是非と見極め方
ーー調査体制の違いについて教えてください。
不祥事によって毀損(きそん)したレピュテーションの回復に向けて対外公表が必要となる場合、外部からの信頼性を高める手段として「独立性を有する第三者委員会」の設置が考えられます。
主な対象は、社会的な注目度が高く、役員の責任が問われるような重大な事案です。
また、監督官庁からの要請(例:金融庁による報告徴求命令など)に応じる場合もあります。
一方で、上記以外のケースにおいても第三者委員会を設置する会社が多すぎます。第三者委員会はすごく費用が掛かるため、企業にとって過度な負担となることが懸念されています。
社内調査委員会の場合には、調査主体によってその目的や機能が異なります。例えば、取締役会は内部統制の改善の要否、監査役・監査委員会は取締役の責任の有無、指名委員会は取締役や執行役の適格性判断など、目的に応じて使い分けがなされています。
ーー外部弁護士などを含む外部調査委員会と、日弁連のガイドライン(以下、ガイドライン)に準拠する第三者委員会の違いは何ですか。
実は、ガイドラインには実務上困る点があります。
1点目は「報告書の公表前に企業側に開示しない」という原則です。
第三者委員会の委員は、依頼元企業を全く知らない人が担当するため、会社概要など基本的な事実関係に誤りや誤解がないか、企業側にファクトチェックしてほしい場面があります。
一方で、報告書起案の事前開示の是非について、専門家でも意見が分かれることが多い。
私は事実認定部分を事前に開示すると、そこから責任や改善策の方向性が予想できてしまうため、事前開示には否定的ではあります。
また、報告書には原因究明と改善策の提言が含まれるため、報告書の受領後すぐに改善策を公表したい場合には、事前に内容を把握できないため、ガイドラインには準拠できません。
2点目は「責任認定を行う場合、第三者委員会は対象者に弁解の機会を設けているのか」という点です。
実際のヒアリングでは、第三者委員会の都合で聞きたいことを聞くが、調査対象者に対して、被疑事実を伝えて、答弁があるかどうかという聞き方はしていません。
ガイドラインに準拠した場合、弁解の機会を与えずに責任認定を行うことになるため、その人の信用や名誉を不当に傷つけるおそれがあります。
そのため、私が第三者委員会を担当する場合には、ガイドラインはあくまで参考として、完全に準拠するとは明言しないことが多いです。
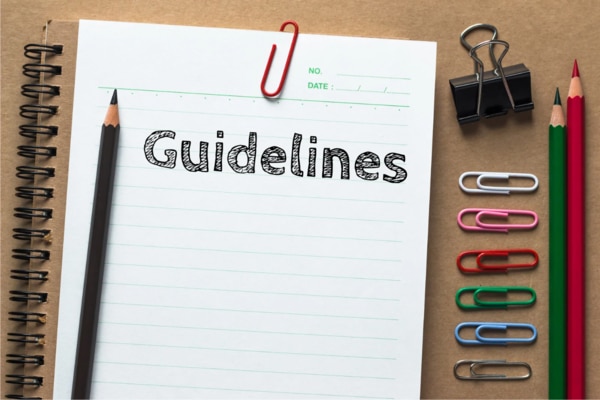
ーーガイドラインに準拠することが“金科玉条”である、というメディアや世論の見方についてどのように感じますか。
担当した弁護士が、ガイドラインに準拠した理由、あるいは準拠しなかった理由について、報告書や記者会見などで、素人向けに丁寧な説明をする必要があると考えています。
私が大きな事案に関する報告書を公表する際には、仮に記者会見を1時間行う場合、そのうち半分くらいの時間を使って、報告書の内容を丁寧に説明するようにしています。
ジャーナリストの方々も独自の視点は持っていますが、必ずしもガバナンスや法律に精通しているわけではありません。法的な観点から分かりやすい解説を重視しています。
記者会見の成功は、発表した内容について、参加者の過半数がきちんと理解できたかどうかだと思っています。
ーー報告書の受領時における企業側の望ましい広報対応や、記者会見の必要性について教えてください。
企業と第三者委員会の双方に共通して、社会的な注目度が高い事案では、説明責任を果たすためにも記者会見を開くべきです。
また、記者会見はネガティブキャンペーンのピークになりやすく、それ以降は状況がV字回復していく傾向にあります。
報告書の受領日に、企業側が記者会見を開くかどうかは、ガイドラインへの準拠有無が判断のポイントになります。
ガイドラインに準拠する場合、事前開示されないため、例えば、報告書の公表が15時、第三者委員会の記者会見が17時だとすると、膨大なページ数の報告書を短時間では到底読み切れません。
その結果、会社側のコメントは「報告書を尊重し対応を検討します」といった形式的なコメントにならざるを得ず、報告書の公表時がピリオドになりづらいです。
さらに数日後に再発防止策などを発表する形となり、報道が再度盛り上がってしまいます。実際に、フジテレビの問題でも、報告書の内容と再発防止策に整合性がなく、後日に改めて対策を発表することになり、対応が長引いてしまっています。
私は、ガイドラインに厳格に準拠するよりも、改善策の提言を事前に共有し、企業側に再発防止策を検討してもらう方が望ましいと考えています。
最近では製造業における品質不正が相次いでいますが、調査委員会の委員を務める弁護士は製造現場に関する専門知識を十分に持っていない場合もあり、現実的でない改善策が報告書に含まれてしまう懸念があります。
そのため、企業側と事前に議論や調整を行い、非現実的な理想を突きつけないようにすることも重要です。

実効性ある改善策とは?企業風土の再構築に必要なこと
ーー改善策および再発防止策について、実効性や納得感の観点から考慮すべきポイントは何でしょうか。
難しい問題です。原因分析と改善策は全部つながっているため、原因分析が決まれば、改善策もおのずと決まります。
ただし、数十ページにわたる再発防止策を見ても、多くの場合、心を打たないですよね。
なぜかというと、活字にできる改善策を列挙して「たくさんやっている感」を出して、外形を整えても、中身の企業風土は変わらないんです。企業風土を深く考えていくと、社長の日々の言動で出来上がっているところが一番多いです。例えば、年頭所感で「コンプライアンスが大事」と言っても、不祥事を報告した際に「ふたをしろ」と言われたら社員は会社を信用できません。社長や上司などが自らの考え方や行動を改めることが必要です。
社内外に「本気で取り組んでいる」と感じてもらうためには、コンプライアンス対策に「とことん時間を使うこと」が重要です。
過去にある会社のコンプライアンス委員会の委員長を務めた際に、経営幹部に対して、年間100時間に及ぶコンプライアンスとガバナンスの研修を実施しました。
2000字の論文を10本書いてもらい、それをもとに勉強会も開きました。社員研修についても、受け身で聞くだけの座学ではなく、自ら考えて、みんなで議論する形、例えばゲーミフィケーションを取り入れた主体的に参加できる研修設計が望ましいです。
年に1回、1~2時間だけの研修ではどうしても忘れてしまいます。「時間」をKPIとして設定し、とことん使うと、本気度が高まり、知識も身に付きます。
他には、「人事制度基準の見直し」も必要です。社員は人事制度基準に沿って行動するため、ここにコンプライアンス要素をいかにうまく組み込むかが鍵となります。
例えば、売上や利益といった定量基準よりも、コンプライアンス研修などの定性基準を重視することで、良い仕事をしないといけないと思うようになります。
また、将来のマネジメント候補者が30~40代の頃にコンプライアンスや監査部門を経験することで、コンプライアンスが企業価値の向上に寄与することを理解してもらうことも有効です。
一方で最近では、「不正をどう発見するか」よりも「不正の発生リスクが高いところを事前に明らかにすること」が重要視されるようになっています。
内部通報や内部監査による発見に頼りすぎると、いつまでも後手に回り、組織的な不正は発見しづらいです。そのため、現在では「プレッシャーがかかりやすい」「悪い誘惑が生じやすい」など、高いリスクがある業務や部署を事前に検知し、一歩先で対処する取り組みが出てきています。
広報担当者に求められるリーダーシップと権限
ーー危機管理広報で重要なポイントはありますか。
緊急時において、社内の意見は「非を認めて謝罪すべき派」と「自らの見解は主張すべき派」の大きく2つに分かれることが多く、おおむね後者のように強気な姿勢は批判されやすい。
また、経営者の中には、広報に任せればうまくいくと勘違いしている人も一定数います。
しかし、危機管理広報が「大成功」「素晴らしい」と評価されることはほとんどありません。
不祥事が発生した時点で、企業のレピュテーションは落ちるところまで落ち、記者会見で厳しく批判されるのは当たり前です。
その上で、「必要以上に批判されないためにはどうすべきか」「今後どのようにリカバリーしていくか」など獲得目標を設定する必要があります。「うまく言い逃れしたい/主張すべき」などと思うと、ドツボにはまってしまいます。
一方、広報部門が社内で十分な権限を持ってないことが多く見受けられます。
なかには、緊急対策会議に広報担当者が参加しておらず、資料作成や舞台設営のみを任されるというとこともあります。
緊急時には、事実関係や現在の状況を正確に把握し、コンプライアンスやガバナンスの観点を踏まえた上で、危機管理広報の獲得目標や情報開示範囲の是非などについて、広報戦略を立案・提言する役割が求められます。
そのためには、個別の事案を正確に理解・把握する「事実レベル」と、それらを適切に判断・構築できる「知識レベル」の両方を備えていないと、広報としてリーダーシップを発揮することは難しいです。

ーー中村先生が判断に迷うときに立ち返る根本的な考え方や大切にしていることを教えてください。
『真っ当なことをやらなければならない』ということです。
第三者委員会や社内調査委員会の場では、“いかがわしい要素”が必ず入ってきてしまいます。
例えば、役員が後ろ向きな発言をして、関係者がそれを擁護したり、調査の範囲や公表の是非について悩んだりと。緊急時には、立場の異なる多くの人からさまざまな意見が出てきて、一枚岩になれないケースが非常に多いです。
そんなときに私がよく言うのは、家に帰って、家族に対して、今日こんな仕事をしてきたと言えないような仕事はやめようと。
そんなときこそ、駆け引きや損得なしに、『真っ当なことをすること』が何よりも大切だと思います。
本記事の内容をさらに深く掘り下げたい方には、インタビューにご登場いただいた中村直人氏による書籍をご一読いただくことをおすすめします。
『ガバナンスを語る』(商事法務、2025年6月発売)
著者:中村 直人
長年にわたり企業法務の現場で活躍されてきた中村氏が、経営と法、そして社会との関係性について自身の視点で綴った一冊です。組織のガバナンスを真に機能させるために必要な考え方や実務への示唆が詰まっています。
📖書籍の詳細はこちら
※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。
▼“不祥事”の影響を最小限に 「危機管理広報プログラム」メニュー資料をダウンロード
▼“伝わり響く”社長発信をサポート「トップコミュニケーション・プログラム」メニュー資料をダウンロード
▼“その表現、大丈夫?”発信前に確認できる「感情リスクチェックシート」をダウンロード
▼関連記事
・危機管理広報の鍵は“初動対応” 今できる備えとは?元記者が解説
・メディアトレーニング 研修の内容や参加時のポイントを詳しく解説
・トップコミュニケーションで注意することは?元記者が解説する「3つのポイント」